�@�@�@�ٗђn����h�g���~�}�Ɩ��戵�K��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����20�N�R���R��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�K����P��
���� |
����28�N�T��31���P�ߑ�W�� |
�ߘa�Q�N�S��17���P�ߑ�18�� |
�@�ٗђn����h�g���~�}�Ɩ��戵�K���i���a45�N���h���P�ߑ�T���j�̑S�������̂悤��
��������B
�ڎ�
�@��P�́@�����i��P���E��Q���j
�@��Q�́@�~�}�����i��R���`��U���j
�@��R�́@�~�}�����i��V���`��24���j
�@��S�́@��Ë@�֓��i��25���`��27���j
�@��T�́@�~�}�����Ԃ̎戵�����i��28���E��29���j
�@��U�́@�~�}�Ɩ��v�擙�i��30���`��34���j
�@��V�́@���}�蓖���̕��y�[���i��35���`��37���j
�@��W�́@�G���i��38���`��40���j
�@�@�@��P�́@����
�@�i�ړI�j
��P���@���̋K���́A�ٗђn����h�g���~�}�Ɩ��Ɋւ�����{�s�K���i���a45�N�K����
�@�W���j�̎{�s�ɂ��ĕK�v�Ȏ������߁A�~�}�Ɩ��̔\���I�ȉ^�p��}�邱�Ƃ�ړI��
�@����B
�@�i�p��̈Ӌ`�j
��Q���@���̋K���ɂ�����p��̈Ӌ`�́A���̊e���ɒ�߂�Ƃ���ɂ��B
�@(�P)�@�~�}�Ɩ��Ƃ́A�ٗђn����h�g���~�}�Ɩ��Ɋւ������Q���ɋK�肷��ق��A
�@�@���h�@�i���a23�N�@����186���j��Q���X���ɒ�߂�Ɩ��������B
�@(�Q)�@�~�}���̂Ƃ́A�@��Q���X���y�я��h�@�{�s�߁i���a36�N���ߑ�37���j��42��
�@�@�ɒ�߂�~�}�Ɩ��̑Ώۂł��鎖�̂������B
�@(�R)�@��Ë@�ւƂ́A��Ö@�i���a23�N�@����205���j�ɒ�߂�a�@�y�ѐf�Ï��������B
�@(�S)�@���}���u���Ƃ́A�~�}�����̍s�����}���u���̊�i���a53�N���h��������Q���j
�@�@�ɒ�߂鏈�u�������B
�@(�T)�@�~�}�~���m�Ƃ́A�~�}�~���m�@�i�����R�N�@����36���j�ɒ�߂�҂������B
�@(�U)�@�~�}�~�����u�Ƃ́A�~�}�~���m�@�{�s�K���i�����R�N�����ȗߑ�44���j��21����
�@�@��߂鏈�u�������B
�@(�V)�@�w���~���m�Ƃ́A�~�}�Ɩ��Ɍg���E���̐��U����̂�����i����26�N���h����
�@�@�h�~��103���j�ɒ�߂�v�������~�}�~���m�������B
�@(�W)�@�����ǖ@�K�Ƃ́A�����ǂ̗\�h�y�ъ����ǂ̊��҂ɑ����ÂɊւ���@���i��
�@�@��10�N�@����114���j�������B
�@(�X)�@�w�ߒS�����Ƃ́A�ٗђn����h�g�����h�{���ʐM�K����Q���Q���ɒ�߂�҂�
�@�@�����B
�@(10)�@�����w���Ƃ́A�~�}�Ɩ����{��i���a39�N�����b������U���j��16���ɒ�߂�
�@�@�w���������B
�@(11)�@�h�N�^�[�w���Ƃ́A�~�}��×p�w���R�v�^�[��p�����~�}��Â̊m�ۂɊւ����
�@�@�ʑ[�u�@�i����19�N�@����103���j��Q���ɒ�߂�w���R�v�^�[�������B
�@(12)�@�h�N�^�[�J�[�Ƃ́A��t���~�}����ɔh������ԗ��������B
�@(13)�@�c�l�`�s�Ƃ́A�c�l�`�s�����v�̂ɂ��āi����18�N�㐭�w���j�ɒ�߂��Ã`
�@�@�[���������B
�@(14)�@���f�B�J���R���g���[���Ƃ́A�~�}���ꂩ���Ë@�ւɔ��������܂ł̊ԁA�~
�@�@�}�~���m�������{�����Ís�ׂɂ��Ĉ�t���w���y�юw���y�я������тɌ�����
�@�@���Ƃɂ��A�����̈�Ís�ׂ̎���ۏ���̐��������B
�@�@�@��Q�́@�~�}����
�@�i�~�}���̕Ґ��j
��R���@�~�}���́A���߁i���a36�N���ߑ�37���j��44���P���ɒ�߂�Ґ��Ƃ��A�~�}��
�@�̂̒��x�ɂ����������邱�Ƃ��ł���B
�@�i�����̎��i�j
��S���@�����́A���̊e���ɒ�߂�ꂽ���i��L����҂łȂ���Ȃ�Ȃ��B
�@(�P)�@�~�}�~���m
�@(�Q)�@�~�}�Ɩ��Ɋւ���u�K�ŁA���h�w�Z�̋���P���̊�i����15�N���h��������R
�@�@���j�ɒ�߂鎞�Ԉȏ�̍u�K���C��������
�@(�R)�@�~�}�Ɩ��Ɋւ���u�K�̉ے����C�������҂Ɠ����ȏ�̊w���o����L����҂��
�@�@�߂錏�i���a57�N���h��������P���j�ɊY�������
�@(�S)�@���h�����F�߂��
�@�i�~�}�����j
��T���@�~�}�����i�ȉ��u�����v�Ƃ����B�j�́A�O���P���A��Q���y�ё�R���ɒ�߂�
�@�҂ŁA���h�m���ȏ�̊K���ɂ�����̂Ƃ���B
�Q�@�����́A�~�}����̏�I�m�ɔc������ƂƂ��ɁA�������w���ē��A�~�}�Ɩ���
�@�~���ɍs���悤�ɓw�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�i�����̕����j
��U���@�����́A�~�}�Ɩ������{����ꍇ�́A�~�}�����͊����h�~�ߋy�ѕۈ��X�𒅗p��
�@����̂Ƃ���B�������A������̈��S���m�ۂ���Ă���ꍇ�ɂ́A�ۈ��X�ɑウ�ăA�|
�@���L���b�v���𒅗p���Ă��ǂ����̂Ƃ���B
�@�@�@��R�́@�~�}����
�@�i�o����j
��V���@�~�}���̏o����́A�Ǔ���~�Ƃ��A�e���̊NJ����́A�i�ʕ\��P�j��������
�@����B�������A���h�g�D�@�i���a22�N�@����226���j��39����тɑ�44���̋K��Ɋ��
�@���v���A���͏��h���A�ʐM�w�߉ے��A���h�����y�ѕ������i�ȉ��u�������v�Ƃ����B�j
�@�����ɕK�v�ƔF�߂��ꍇ�́A���̌���łȂ��B
�@�i�o��w�߁j
��W���@�ʐM�w�߉ے����͏������́A�~�}���̂����������|�̒ʕ�������Ƃ��A����
�@�~�}���̂������������Ƃ�m�����Ƃ��́A���Y���̂̔����ꏊ�A���̊T�v�A���a�҂̐l
�@���y�я��a�̒��x���i�ȉ��u���ē��e���v�Ƃ����B�j���m���߁A�����ɏ��v�̋~�}����
�@�o�ꂳ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̏ꍇ�ɂ����āA���ē��e���ɂ��A�w�����A���h���A
�@�~�����y�ё��̋~�}�����o�ꂳ������̂Ƃ���B
�Q�@�w�ߒS�����́A���ē��e������A���}�ɉ��}�蓖���̕K�v������Ɣ��f�����Ƃ��́A
�@�ʕ�ғ��Ɍ����w�����s�����̂Ƃ���B
�R�@�����́A�o��r��ɂ����鎖�ē��e���̏��y�ь��ꓞ����̏ɂ��A�w�����A
�@���h���A�~�����y�ё��̋~�}���̉����v�����s�����̂Ƃ���B
�@�i����̎w���j
��X���@�~�}����̎w���͑����Ƃ���B�������A��K�͋~�}���̔������ɂ́A�w���{����
�@�������w�����Ƃ�A�����͂����⍲������̂Ƃ���B
�Q�@�����́A�����̏��a�҂��������Ă���~�}����ɂ����ẮA�ʂɒ�߂�Ǐ��ЊQ�Ή�
�@�}�j���A���ɏ]���A�~�}�w���҂Ƃ��ď��a�ґΉ��ɂ�������̂Ƃ���B
�@�i���a�҂ɑ��鏈�u�j
��10���@���ꓞ�����y�є����r��́A�K�v�ɉ����ēK�ȉ��}���u�����{���A���₩�Ɉ�
�@�Ë@�ւɔ���������̂Ƃ���B
�Q�@�~�}�~�����u���́A���a�҂���Ë@�ւɈ����p���܂ł̊ԁA���͈�t���~�}����ɓ�
�@������܂ł̊ԂɁA�~�}�~�����u�����{���Ȃ���Γ��Y���a�҂̐����Ɋ댯������A��
�@�͂��̏Ǐ������邨���ꂪ����ƔF�߂���ꍇ�ɍs�����̂Ƃ���B
�R�@�~�}�~���m�́A���f�B�J���R���g���[���̐��̂��ƈ�t�̋�̓I�Ȏw�����Ȃ���
�@�A�~�}�~�����u���s���Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�S�@�O���ɋK�肷���t�́A�����Ƃ��Ċٗђn�惁�f�B�J���R���g���[�����c��ɑ�����
�@��t���͑�O���~�}��Ë@�ւɑ������t�Ƃ���B
�@�i�~�}�~�����u�^�j
��11���@�~�}�~���m�́A�~�}�~�����u���s�����Ƃ��ɋ~���m�@��46���ɋK�肷��~�}�~��
�@���u�^�Ɍ����J���ȗ߂Œ�߂鎖����x�Ȃ��L�ڂ��A��������̋L�ڂ̓�����T�N��
�@�ۑ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A�~�}�����L�^�[�i�l����P���j�ɋ~�}�~�����u���L
�@�ڂ����ꍇ�́A������~�}�~�����u�^�Ƃ��邱�Ƃ��ł���B
�@�i���������҂̎戵���j
��12���@�����́A�~�}�Ɩ��̎��{�ɍۂ��A���a�Җ��́A���̊W�҂����������ꍇ�́A
�@�����������Ȃ����̂Ƃ���B
�Q�@�O���̏ꍇ�ɂ����đ����́A���ۂ̗��R��ڍׂȏ����~�}�����L�^�[�ɋL�ڂ��A
�@�����m�F���i�l����Q���j�̕s�����������ɓ��Y���a�Җ��͂��̊W�҂̏����āA
�@�~�}�����L�^�[�ɓY�t������̂Ƃ���B�������A���Y���a�Җ��͂��̊W�҂̏����ɂ�
�@���ẮA����̏��ɂ��K�{�Ƃ�����̂ł͂Ȃ��B
�@�i�D���ғ��̎戵���j
��13���@�~�}�v��������o�ꂵ�����̂̂����A�D���Җ��͂���ɏ�����҂ň�Ï��u��K
�@�v�Ƃ��Ȃ��ƔF�߂�ꂽ�ꍇ�́A�Ƒ����͌���x�@�����Ɉ��n���A�O���̋K������p��
�@����̂Ƃ���B
�@�i�W�Q�A�\�͍s�҂̎戵���j
��14���@�������~�}�Ɩ����ɁA�W�Q�y�і\�͍s�ׂ����ꍇ�̑Ή��́A���̊e���̂Ƃ�
�@��Ƃ���B
�@(�P)�@�~�}�Ɩ��̌p���������Ƃ��A�������\�͍s�ד��ɂ�蕉�������ꍇ�́A���₩��
�@�@�~�쏈�u����邱�ƁB
�@(�Q)�@�W�Q�s�ׂɂ��~�}�Ɩ��̌p�����{������ȏꍇ�́A���₩�Ɏ��̊T�v��ʐM�w
�@�@�߉ۂɕ��A�K�v���̑����v�����s���B�܂��A���̏����ɕK�v������ꍇ�́A��i
�@�@�̏o��v�����čs�����ƁB�����̔�Q�̌y�d�ɂ�����炸�A�ʐM�w�߉ۂ�ʂ���
�@�@��Ɍx�@���̏o��v�����s���A�x�@���̌��ꓞ����W�Q�y�і\�͍s�ׂ̏𑬂₩
�@�@�ɕ��A�����̈��S�m�ۋy�ы~�}�Ɩ��ւ̋��͂��˗�����B
�@(�R)�@�W�Q�҂Ƃ̑Ή��́A�����A����I�ƂȂ��đ�����h�����邱�Ƃ̂Ȃ��悤�ɁA��
�@�@�Ò����ɋB�R����ԓx�Őڂ��邱�ƁB
�@(�S)�@����ۑ��ɓw�߁A�؋��ƂȂ镨����ڌ��҂��m�ۂ��A�ؐl�̈˗�������ƂƂ��ɁA
�@�@�Z���A�����A�d�b�ԍ��A�ڌ��ʒu�y�іڌ����e�����L�^���邱�ƁB
�@(�T)�@�������s�����[�u�����a�ҋy�щƑ����̊W�҂ɐ������A�~�}���̍s����
�@�@�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�i�����h�~��j
��15���@�������́A���������~�}�����̎��{�ɍۂ��A�����ǖ@�K�ɋK�肷�銴���Ǔ��̉�
�@�����A�����̂����ꂪ�������ꍇ�́A���₩�ɑ[�u���u����ƂƂ��ɏ��h���֕�
�@������̂Ƃ���B
�Q�@�����́A�~�}�����̎��{�ɍۂ��A�����ǖ@�K�ɋK�肷�銴���Ǔ����A�����̂���
�@�ꂪ�������ꍇ�́A�����y�ы~�}�����ԓ��̉����ɗ��ӂ��A�����ɏ���̏��ł��s���A
�@���̎|���������ɕ���ƂƂ��ɁA���Y���a�҂ɑ����t�̐f�f���ʂ��m�F���A��
�@���ɕK�v�ȑ[�u���u������̂Ƃ���B
�R�@�O���̏���̏��ł��s���ꍇ�́A���̊e���ɒ�߂����Ƃ���B
�@(�P)�@�ٗя��h��
�@(�Q)�@�W�y���h��
�@�i��t�̋~�}����v���j
��16���@�w�ߒS�������́A�����́A���ē��e������A��t��K�v�Ɣ��f����A�~�}����
�@�ւ̗v�����s�����̂Ƃ���B
�Q�@�O���̗v���ɂ����ẮA���̊e���ɒ�߂����@�Ƃ���B
�@(�P)�@�h�N�^�[�w���v��
�@(�Q)�@�h�N�^�[�J�[�v��
�@(�R)�@���������t�v��
�@(�S)�@�c�l�`�s�v��
�R�@�����̏��a�҂��������Ă���~�}����Ⴕ���́A���ꂪ�^���鎖�ē��e���ɂ�����
�@�́A��t�̋~�}����h���̗L���ɂ�����炸�A�����Ǐ��ЊQ�������ɂ�����Q�n
�@�c�l�`�s�h���v���}�j���A���Ɋ�Â������s�����̂Ƃ���B
�@�i���a�҂̔��������j
��17���@���a�҂����̊e���̂����ꂩ�ɊY������ꍇ�́A���Y���a�҂�������Ȃ����̂�
�@����B
�@(�P)�@���炩�Ɏ��S���Ă���ꍇ
�@(�Q)�@��t�����S���Ă���Ɣ��f�����ꍇ
�@(�R)�@���a�҂����炩�Ɋ����ǖ@�K��U���Q���y�ё�R���ɋK�肷�鎾�a�ɂ�鏝�a
�@�@�Җ��͓��@��W���Q���ɋK�肷��a���ۗ̕L�҂ł���ꍇ
�Q�@�O���̏ꍇ�ɂ����āA�W�@�֑��݂̏���A�������˗����ꂽ�ꍇ�ɂ����ẮA
�@�������邱�Ƃ��ł�����̂Ƃ���B
�@�i�W�҂̓���j
��18���@�����́A�~�}�Ɩ��̎��{�ɍۂ��A���a�҂̊W�Җ��́A�x�@������������߂���
�@���́A���}���u�Ɏx�Ⴊ�Ȃ�����A�w�߂Ă���ɉ�������̂Ƃ���B
�Q�@�����́A�����N�Җ��́A�ӎ����ɏ�Q������҂Ő���Ȉӎv�\�����ł��Ȃ����a�҂�
�@��������ꍇ�́A�ی�ғ��W�҂̓�������߂���̂Ƃ���B
�@�i�v�ی�ғ��̎戵���j
��19���@�����́A���a�҂������ی�@�i���a25�N�@����144���j�ɒ�߂�v�ی�Җ��͔�
�@�ی�҂Ɣ��������ꍇ�ɂ́A�s�����A���ꓙ�̒S�������ɑ��āA�������Ë@�֖��y
�@�я��a�҂̏��a���x���Y�Ɩ��̐��s�ɂ�����A���ɕK�v������ꍇ�ɂ͘A�������
�@�̂Ƃ���B
�@�i�Ƒ����ւ̘A���j
��20���@�����́A���a�҂̏��a�ɂ��K�v������ƔF�߂�Ƃ��́A���̎҂̉Ƒ�����
�@���A���a���x�y�я�A������悤�w�߂���̂Ƃ���B
�@�i�x�@�ւ̘A���y�ь���ۑ��j
��21���@�������͎w�ߒS�����́A���̊e���Ɍf����~�}���̂����������ꍇ�A�����Ɍx�@
�@���ɒʕ�ƂƂ��ɁA�~�}���͏��a�҂ɑ����}���u�����{���A�\�Ȕ͈͂ɂ�����
�@����ۑ��ɗ��ӂ���B
�@(�P)�@�����s��
�@(�Q)�@���Q
�@(�R)�@��ʎ���
�@(�S)�@�J���ЊQ
�@(�T)�@���炩�Ɏ��S���Ă���ꍇ
�@�i�~�}�������j
��22���@�������͋~�}�~���m�́A�~�}�����~�}����ɏo�ꂵ�A����ɂ�����~�}�����̏�
�@�u�̊T�v���~�}�����L�^�[�ɂ��A�������ɕ��s�����̂Ƃ���B
�Q�@�������͋~�}�~���m�́A���a�҂��������Ë@�ւɈ��n�����ꍇ�́A�~�}���̊ώ@��
�@�����L�ڂ��������m�F������t�ɓn���A���Y��t�̏��f�����������~�}�����L�^�[�ɋL
�@�^���Ă������̂Ƃ���B�������A���Y��t���珉�f���������̏����Ɏ��Ԃ�v���A�o��
�@�̐��Ɏx����������ƔF�߂��ꍇ�́A���̌���ł͂Ȃ��B
�R�@�~�}�~���m�́A�~�}�Ɩ��̎��{�ɂ��ċ~�}����i�l����R���j�ɂ��A�����P
�@��ȏ���h���ɕ��s�����̂Ƃ���B
�S�@�������́A���ٓI�ȋ~�}���Ă����������ꍇ�́A�d�v������i�l����S���j�ɂ�
�@����h���ɕ��s�����̂Ƃ���B
�@�i�~�}���j
��23���@���h�����͒ʐM�w�߉ے��́A�~�}�E�~�����̂ɂ����āA���̊e���Ɍf���鎖�̂�
�@���������Ƃ��́A�ЁE�ЊQ������v�́i���a59�N���h�h�Б�267���j�Ɋ�Â��A����
�@���ɋ~�}�E�~�����̑���i�l����T���j�ɂ��A�����͏��h���ɕ��s�����̂Ƃ���B
�@�i���㌟�j
��24���@���f�B�J���R���g���[���Ɋ�Â��A���̊e���Ɍf����~�}���̂ɂ����ẮA�~�}
�@�����̎��㌟�i�ȉ��u���v�Ƃ����B�j�����{���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@(�P)�@�S�x��~��Ԃ̏��a�҂���������ꍇ
�@(�Q)�@�~�}�~�����u�����{�����ꍇ
�@(�R)�@�d�NJO���̏��a�҂���������ꍇ
�@(�S)�@��t��v�������ꍇ
�@(�T)�@���̑��������K�v�ƔF�߂�~�}����
�Q�@�ꎟ���̎��{�҂́A�w���~���m���͋~�}�~���m�̌W�����s�����̂Ƃ���B
�R�@���̎��{�҂́A�ٗђn�惁�f�B�J���R���g���[�����c��őI�C���ꂽ���Y���
�@�@�ւ̈�t���s�����̂Ƃ���B
�@�@�@��S�́@��Ë@�֓�
�@�i��Ë@�ւ̑I��j
��25���@�~�}�������a�҂�������ׂ���Ë@�ւ́A���a�҂̏Ǐ�ɉ�������Ë@�ւƂ���B
�Q�@��Ë@�ւ��瑼�̈�Ë@�ւɏ��a�҂�����i�ȉ��u�]�@�����v�Ƃ����B�j����ꍇ��
�@�́A���Y��t�Ɋ��ғ]�@�����\�����i�l����U���j���o��������̂Ƃ���B�������A
�@���a�҂ً̋}�x�������A��Ë@�ւɂ����Ē�o������ł���|�̐\���o������ꍇ�ɂ�
�@���ẮA�Ə����邱�Ƃ��ł���B
�R�@�O���̓]�@�������s���ꍇ�ɂ́A���Y��Ë@�ւ̈�t���͊Ō�t�悳������̂�
�@����B�������A���Y��t���O���̐\�����ɂ��A���悵�Ȃ����ƂŋN���肤��ӔC��
�@�����Ƃɓ��ӂ��A�������邱�Ƃɂ���āA�����Ə����邱�Ƃ��ł���B���̏ꍇ����
�@�́A��t�ɔ������̏��u���̎w���y�ђ��ӎ������Ĕ���������̂Ƃ���B
�@�i��Ë@�ւƂ̘A���j
��26���@���h���́A�Q�n���~�}��Ñ̐��������c��A�ٗђn�惁�f�B�J���R���g���[����
�@�c��y�тa�`�m�c�n���f�B�J���R���g���[�����c����тɋ~�}�Ɩ��ɊW����@�ւƖ�
�@�ڂȘA�g��}��A�~�}�Ɩ����̌����I�ȉ^�c�ɓw�߂���̂Ƃ���B
�Q�@���h���́A�O���̉^�c�ɓw�߂邽�߂ɁA�w���~���m���w��������̂Ƃ���B
�@�i�\�㒲���j
��27���@�������͋~�}�~���m�́A�S�x�@�\��~���̏��a�҂���Ë@�ւɔ��������ꍇ�́A
�@�]�A�y�ї\�㒲�����s�����̂Ƃ���B
�@�@�@��T�́@�~�}�����Ԃ̎戵����
�@�i���Łj
��28���@�����́A���̊e���ɒ�߂�Ƃ���ɂ��A�~�}�����ԋy�ѐύڎ���ނ̏��ł��s
�@�����̂Ƃ���B
�@(�P)�@������Ł@���P��
�@(�Q)�@�g�p����Ł@���g�p��
�@(�R)�@���ʏ��Ł@���ɕK�v�ƔF�߂�ꍇ
�@�i�~�}�����Ԃɔ����鎑��ށj
��29���@�~�}�����Ԃɂ́A�~�}�Ɩ����{��i���a39�N�����b������U���j��13���ɒ��
�@�鎑��ނ��������̂Ƃ���B
�@�@�@��U�́@�~�}�Ɩ��v�擙
�@�i����~�}�Ɩ��v��j
��30���@���h���́A����ȋ~�}���̂̔��������ꍇ�ɂ�����~�}�Ɩ��̎��{�ɂ��Ă̌v
�@����쐬�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�Q�@���h���́A���N�Q��ȏ�O���ɒ�߂�v��Ɋ�Â��P���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�i�~�}�����j
��31���@���h���́A�~�}�Ɩ��̉~���Ȏ��{��}�邽�ߓ��Y�����ɂ��āA���̊e���ɒ�
�@�߂�Ƃ���ɂ��A�~�}�����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@(�P)�@�n���y�ь�ʂ̏�
�@(�Q)�@��Ë@�֓��̈ʒu�y�ш�Ñ̐�
�@(�R)�@�~�}���̂��������邨����̂���Ώە��̈ʒu�A�\���y�т`�d�c�̐ݒu��
�@(�S)�@���̑��K�v�ƔF�߂鎖��
�@�i�~�}�~���m�̏A�ƑO����j
��32���@�~�}�~���m�̎��i��L�����E���ɂ��ẮA�~�}�~���m�̎��i��L����~�}����
�@�ɑ��čs���A�ƑO����̎��{�v�̂̈ꕔ�����ɂ��āi����26�N���h�~��46���j�Ɋ�
�@�Â��A�a�@���K�����{����ƂƂ��ɁA���猤�C�����{���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A��
�@�I�{���@�ւɂ�鋳����o�Ď��i��L�����E���ɂ��ẮA���猤�C��Ə����邱�Ƃ�
�@�ł���B
�Q�@���h���́A���ԗ{���@�ւ𑲋Ƃ��ē��������~�}�~���m�ɑ��A�O���Œ�߂�A�ƑO
�@����̐��ʂ𑪂邽�߂ɁA�w���~���m�ɑ��čŏI�]�������{�����A��l�ɓ��B����
�@�҂ɑ��A�~�}�~�����u��F�߂���̂Ƃ���B
�@�i�~�}�~���m�̋Z�\�ێ��j
��33���@�~�}�~���m�́A�a�@�O�~���S���v���t�F�b�V���i���ł��邱�Ƃ����o���A���
�@�E��̈���Ƃ��ċZ�\�ێ��ɓw�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�Q�@���h�����͏������́A�~�}�~���m�̎��i��L����~�}�����̍ċ���ɂ��āi����20
�@�N���h�~��262���j�Ɋ�Â��A�~�}�~���m�ɑ��čċ���̑̐����m�ۂ���ƂƂ��ɁA
�@�w�p�y�ыZ�\�ێ��ɕK�v�Ȍ��C����u�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�R�@�~�}�~���m�̍ċ���́A�a�@���K�������Ƃ��邪�A�w�p�W�����H�Z�\����R�[�X��
�@���Ă��ϋɓI�ɎQ�����A�����̑�������ɓw�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�i�����̌��C�y�ьP���j
��34���@�������́A�����ɑ��~�}�Ɩ����~���ɍs�����߂ɕK�v�Ȋw�p�y�ыZ�\�C���ɕK
�@�v�Ȍ��C����u������ƂƂ��ɁA����P�����s���悤�w�߂���̂Ƃ���B
�Q�@�w���~���m�́A���h���A�x�h�ے��y�я������̖����A�O���ɒ�߂�Z�\�ێ��ɑ�
�@���A����P������悷��ƂƂ��ɁA�w���y�я������s�����̂Ƃ���B
�@�@�@��V�́@���}�蓖�̕��y�[������
�@�i���}�蓖���y�[���̐��i�j
��35���@���h���́A���}�蓖�̕��y�[�������̐��i�Ɋւ�����{�v�j�i�����T�N���h�~��
�@41���j�Ɋ�Â��A�Z���ɑ��鉞�}�蓖�Ɋւ��鐳�����m���ƋZ�p�̕��y�����{������
�@����Ȃ�Ȃ��B
�@�i�u�K�̎�t�y�ѐ\���j
��36���@�O���Œ�߂�u�K�̎�ނɂ������u�Ώێҋy�эŏ��J�Ðl���́A���̊e���ɒ�
�@�߂�Ƃ���Ƃ���B
�@(�P)�@���ʋ~���u�K��T�́A�S�Ă̏Z����ΏۂƂ��V���ȏ�ɂĊJ�Â���B
�@(�Q)�@���ʋ~���u�K��U�́A�~���̌���ɑ�������@��̑�����ÐE�y�щ��E���т�
�@�@�~��Ɍg���҂݂̂Ƃ��V���ȏ�ɂĊJ�Â���B
�@(�R)�@�~������R�[�X���͉��}�蓖�u�K��́A�S�Ă̏Z����ΏۂƂ�10���ȏ�ɂĊJ��
�@�@����B
�Q�@���\���[�j���O��p���������^�u�K�ɂ��ẮA�K�v�ɉ����Ď��{������̂Ƃ���B
�R�@���ʋ~���u�K��V���тɏ㋉�~���u�K��ɂ��ẮA�����Ƃ��Ď��{���Ȃ����̂Ƃ�
�@��B
�S�@��P���Œ�߂�u�K��̎�t�ɂ��ẮA�J�×\�������t���̂P�������z�������
�@�݂̂Ƃ��A�����ɂ����铯���Q�ȏ�̍u�K�͎t���Ȃ����̂Ƃ���B
�T�@���h���́A�u�K��̎�ނɉ������\�����i�l����V���j�i�l����W���j�ɂ��\����
�@�����āA�u�K����J�Â�����̂Ƃ���B
�@�i�C���̌�t�y�ѕj
��37���@���h���́A���ʋ~���u�K��T���тɕ��ʋ~���u�K��U���I�������҂ɑ��A����
�@����̍u�K��ɉ������C������t������̂Ƃ���B
�Q�@�u�K��S�������~�}�~���m�́A�O���Œ�߂�C���̌�t���s�����ꍇ�ɂ��ẮA
�@�C���Җ���i�l����X���j�ɂ����h���ɕ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�@�@��W�́@�G��
�@�i�����ؖ��j
��38���@���h���́A�~�}���ɂ���Ë@�ւ֔������ꂽ���a�Җ��͂��̐e������~�}����
�@�̎����ɂ��Ă̏ؖ��\��������A�����Ƒ���Ȃ��ƔF�߂��Ƃ��́A�~�}�o��ؖ����i
�@�l����10���j�ɂ��A������ؖ�������̂Ƃ���B
�Q�@�O���̏ؖ����s����ۂ́A��̎҂̐g���ؖ����ʂ���ƂƂ��ɁA��t�萔��
�@�Ƃ���200�~��������̂Ƃ���B
�@�i���̕\���j
��39���@���h���́A�~�}�Ԃ̓_�������A�h���@���ɂ��~�}�o��̐��ɂ�炸����
�@��Ƃ��́A�ԗ��O�㕔�̌��₷���ʒu�ɕ\���i�ʕ\��Q�j�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�i�ϔC�j
��40���@���̋K���ɒ�߂���̂̂ق��A�~�}�Ɩ����{����ɕK�v�Ȏ����ɂ��ẮA���h
�@�����ʂɒ�߂�B
�@�@�@���@��
�@���̋K���́A����20�N�S���P������{�s����B
�@�@�@���@���i����28�N�T��31���P�ߑ�W���j
�@���̋K���́A����28�N�U���P������{�s����B
�@�@�@���@���i�ߘa�Q�N�S��17���P�ߑ�18���j
�@���̌P�߂́A�ߘa�Q�N�S���P������{�s����B
�ʕ\��P�i��V���W�j
�ٗя��h�� |
�{���ځ@�{���O���ځ@�{���l���ځ@���c���@�x�m�����@�Ԑ��c���@��Ԑ��c���@
�Ԑ��c�{���@�H�����@�H�������@�ԎR���@�V�h�꒚�ځ@�V�h�ځ@�Β��꒚�ځ@�Β�
�ځ@�����꒚�ځ@�����ځ@�����O���ځ@�����@�������@���������@�����
���@���������@���K�����@�풬�@�x�m�����@�x�H���@�������@�����@�ߓ����@�c�ؒ�
�@�z�K���@���O�ђ��@��O�ђ��@�����J�� |
������ |
�����@���{���@�������@���������@�������@�k�������@�h���@�V�h���@��J���@�ԓy��
�@�������@�㊯���@��X���꒚�ځ@��X���ځ@��X���O���ځ@�������@�،˒� |
�k���� |
�{���꒚�ځ@��蒬�@�钬�@��h���@�≺���@�L�����@���L�����@�������@���g���@��
�����@���@�t���@��{���@���˒J���@�ד����@��˒��@�c�J���@�l�b�J���@�哇���@��
�����@��V�c���@������c���@�㑁��c���@���쒬�@�T���˒� |
�q���h�� |
�q�� |
���a���h�� |
���a�� |
���c���h�� |
���c���@�ٗюs��Ӓ� |
�W�y���h�� |
�W�y�� |
�ʕ\��Q
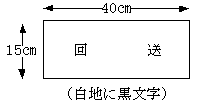 �l����P��
�l����P��
 �l����P���i��11���W�j
�l����P���i��11���W�j
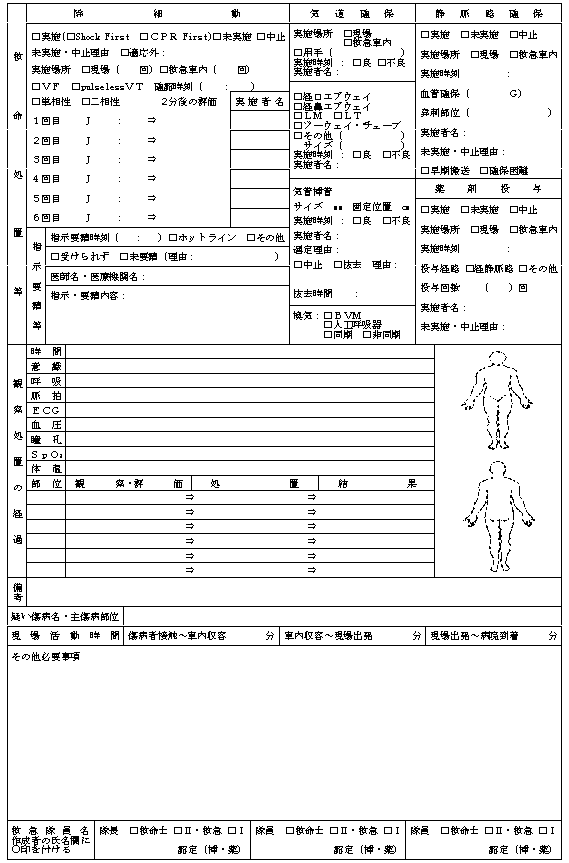 �l����Q��
�l����Q��
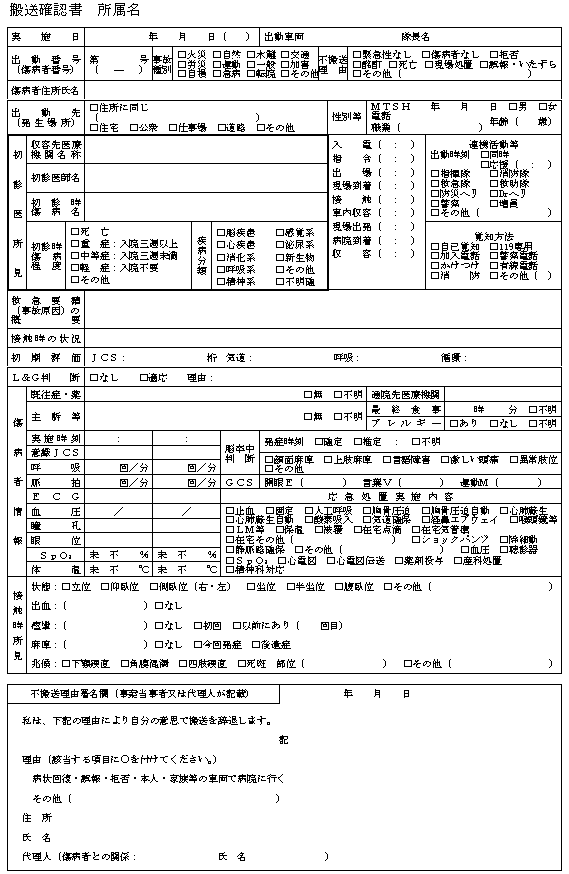 �l����R��
�l����R��
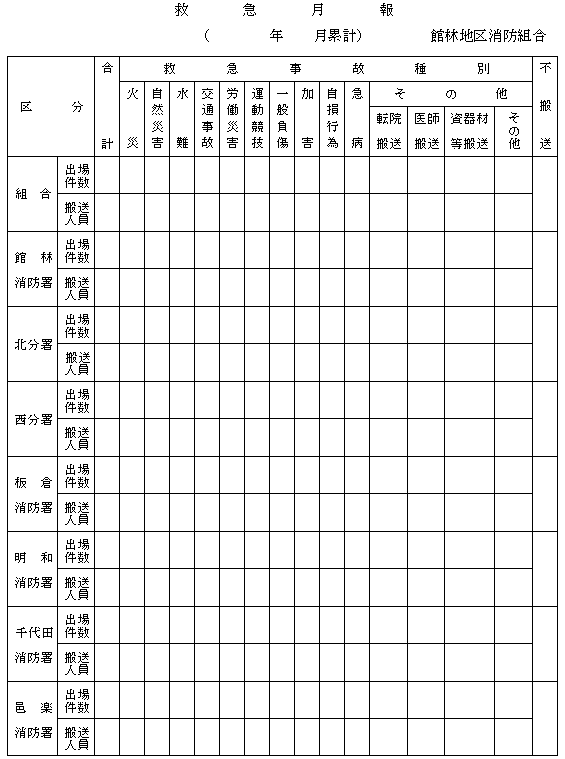 �l����S��
�l����S��
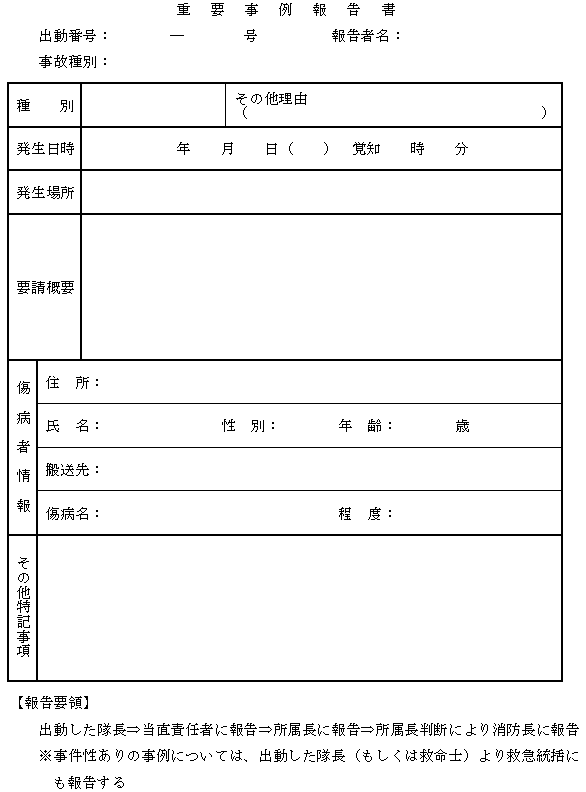 �l����T��
�l����T��
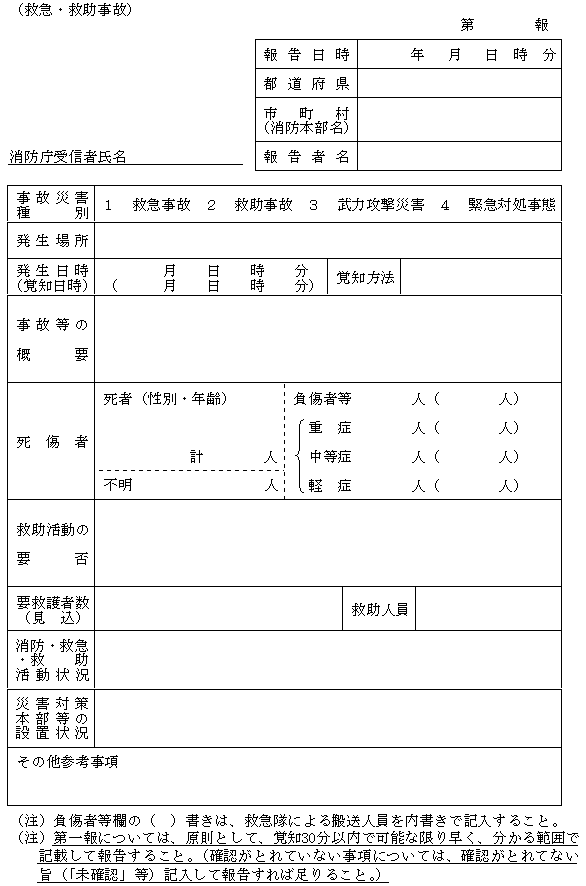 �l����U��
�l����U��
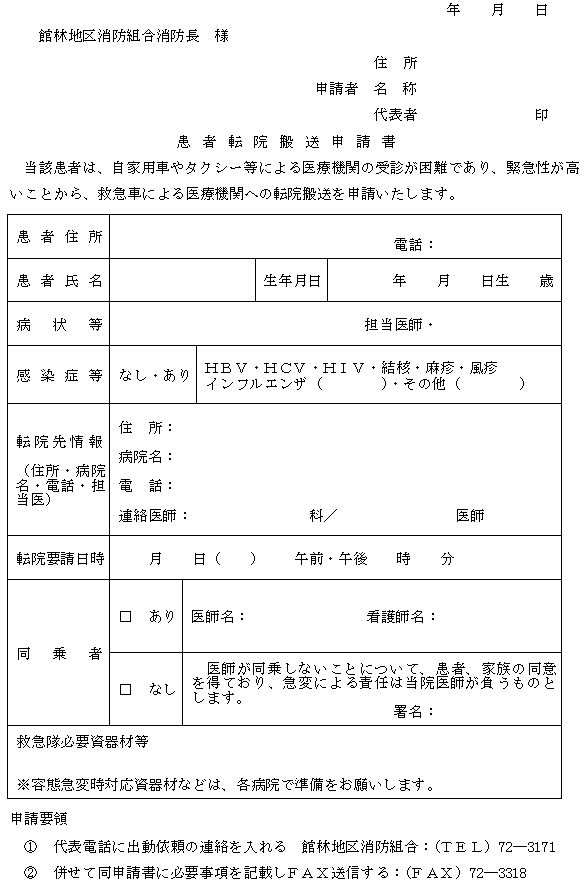 �l����V��
�l����V��
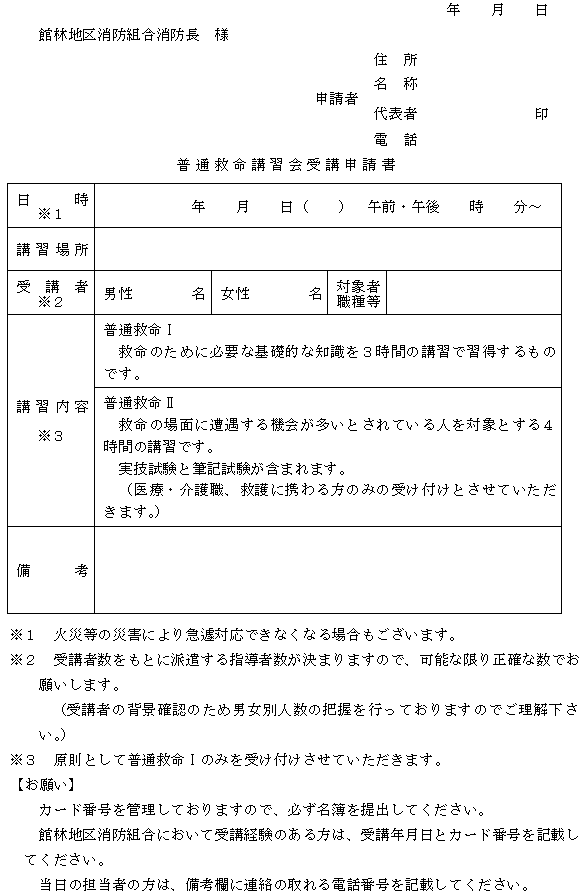
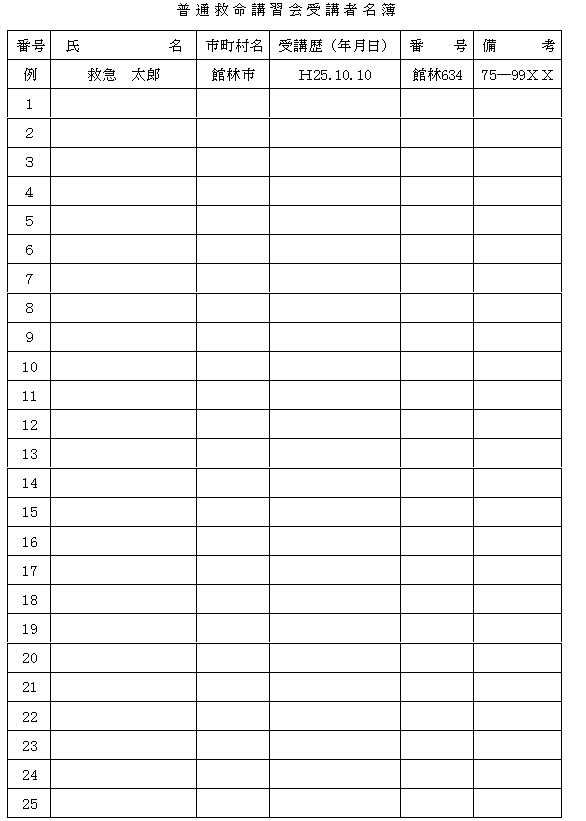 �l����W��
�l����W��
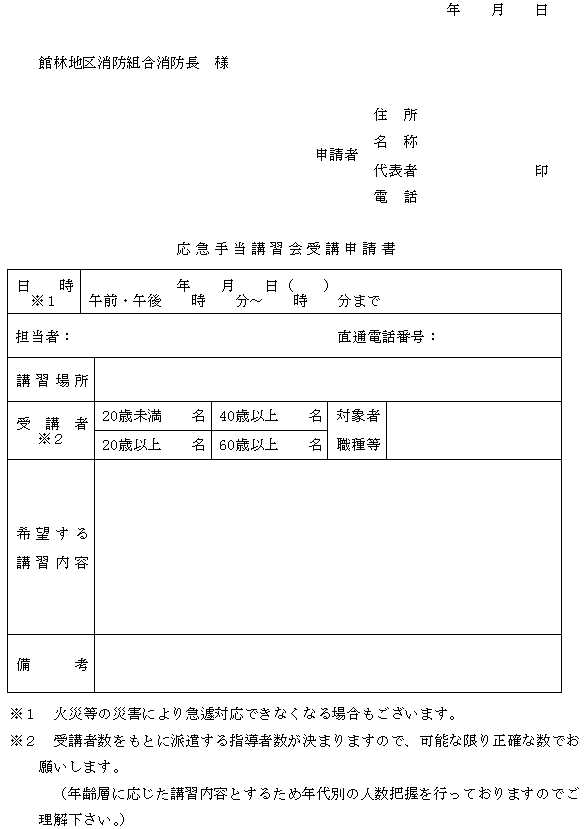 �l����X��
�l����X��
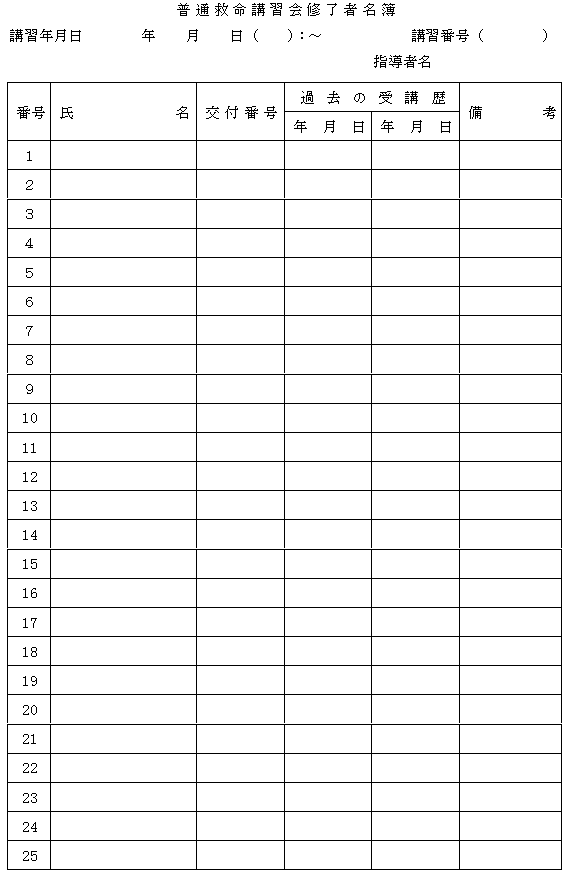 �l����10��
�l����10��
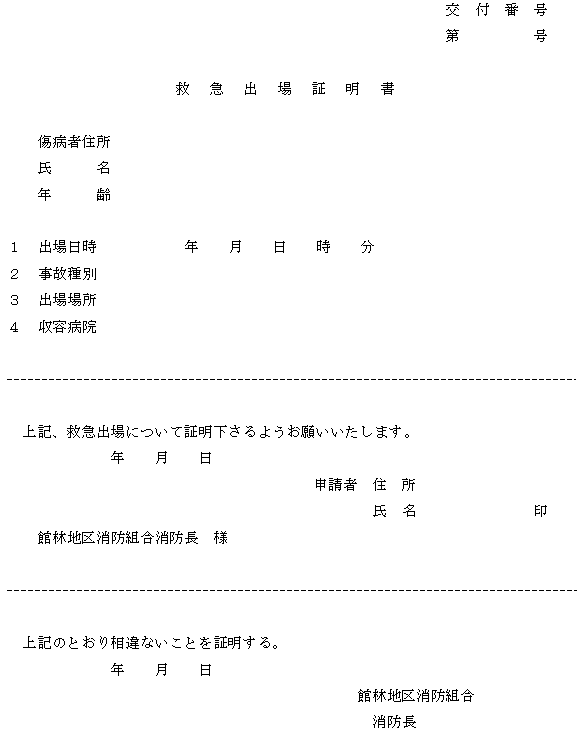
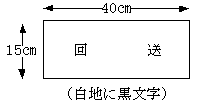 �l����P��
�l����P��
 �l����P���i��11���W�j
�l����P���i��11���W�j
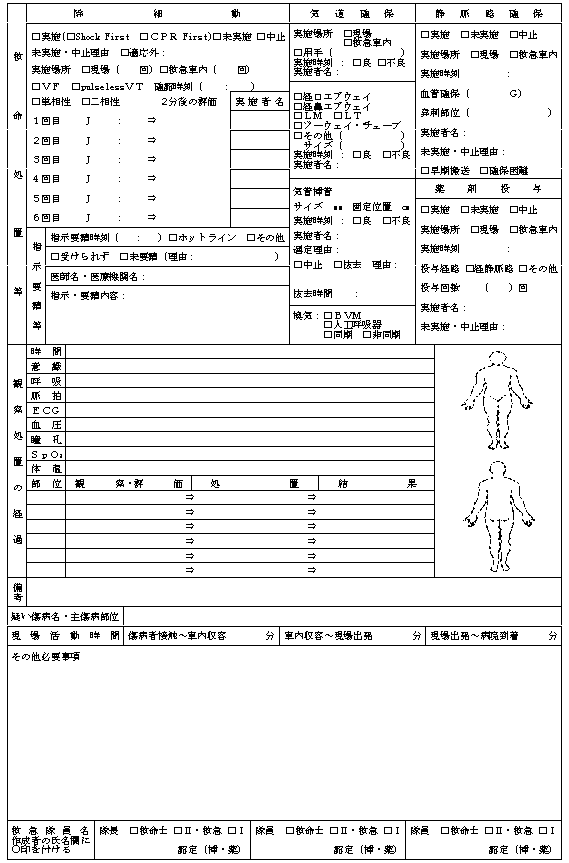 �l����Q��
�l����Q��
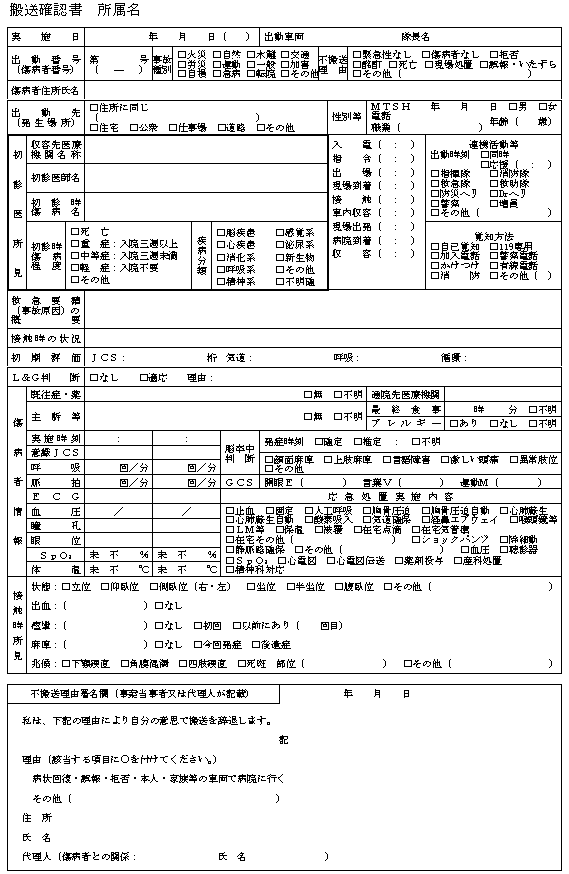 �l����R��
�l����R��
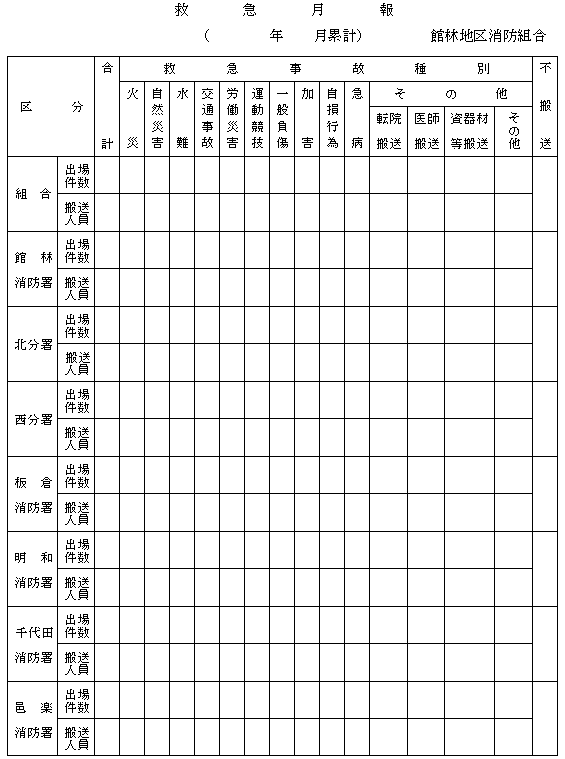 �l����S��
�l����S��
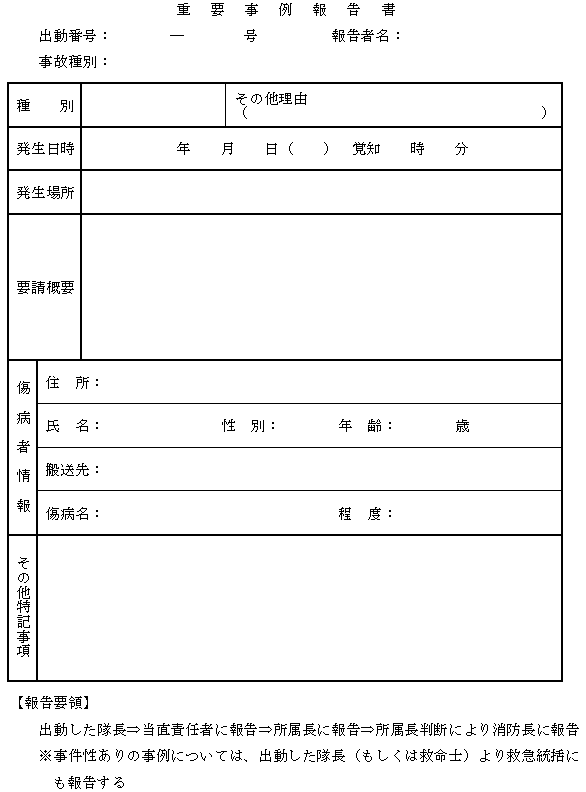 �l����T��
�l����T��
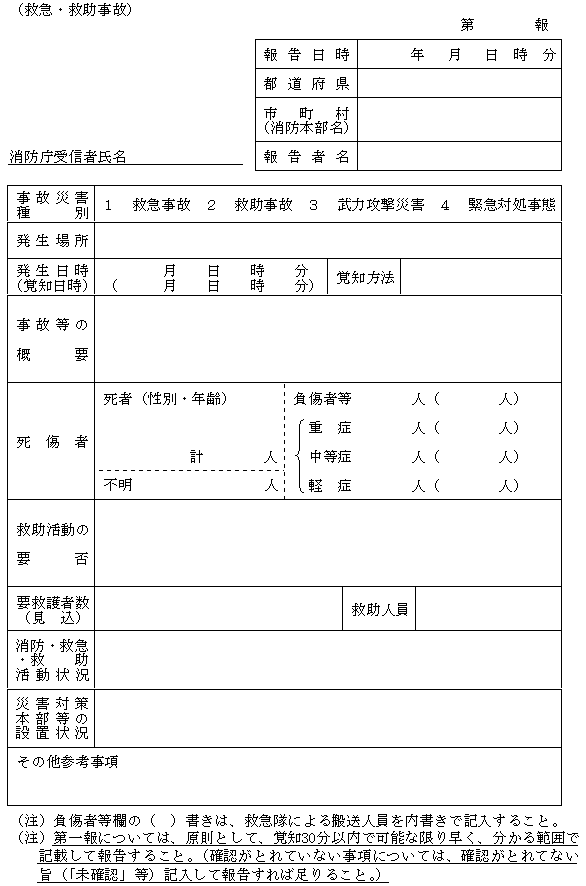 �l����U��
�l����U��
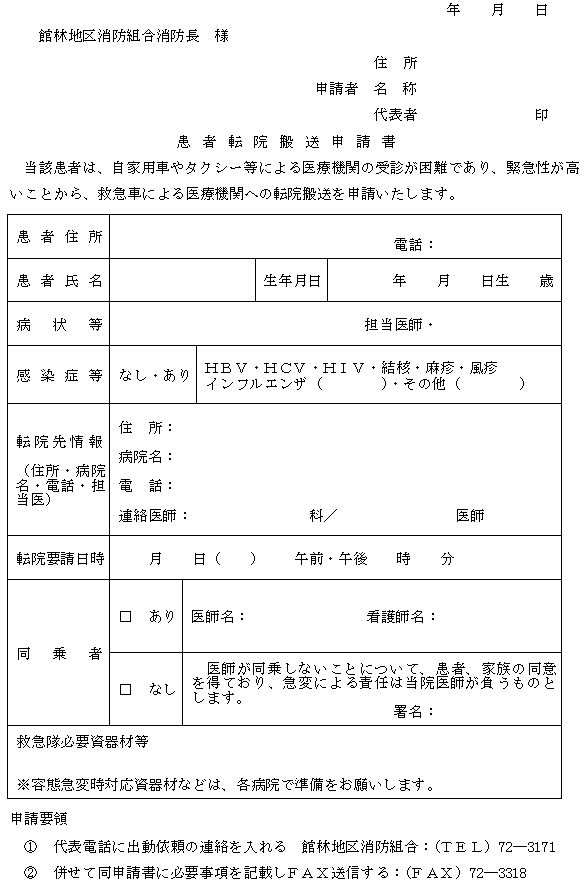 �l����V��
�l����V��
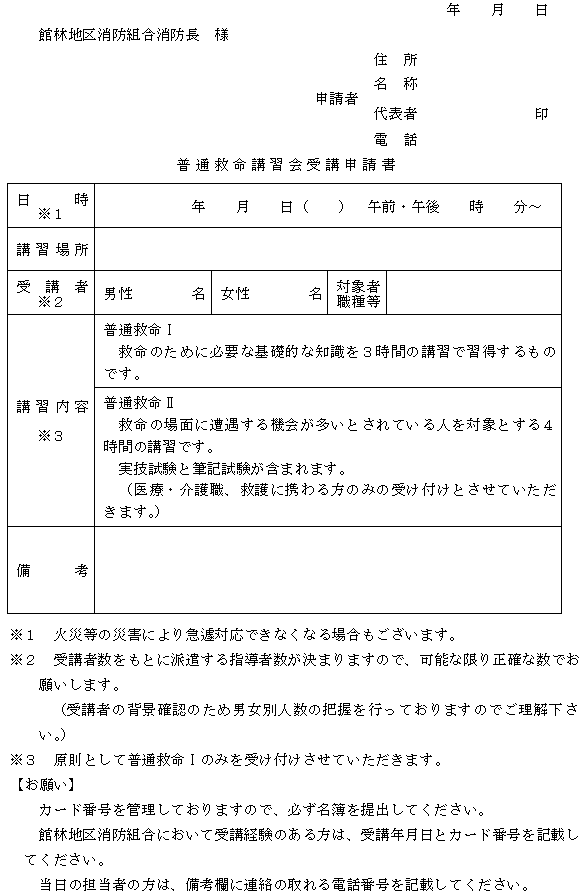
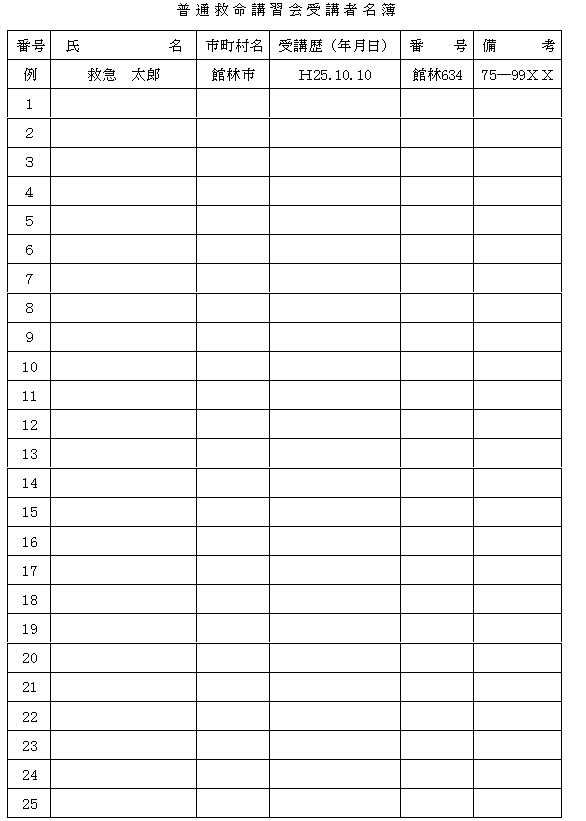 �l����W��
�l����W��
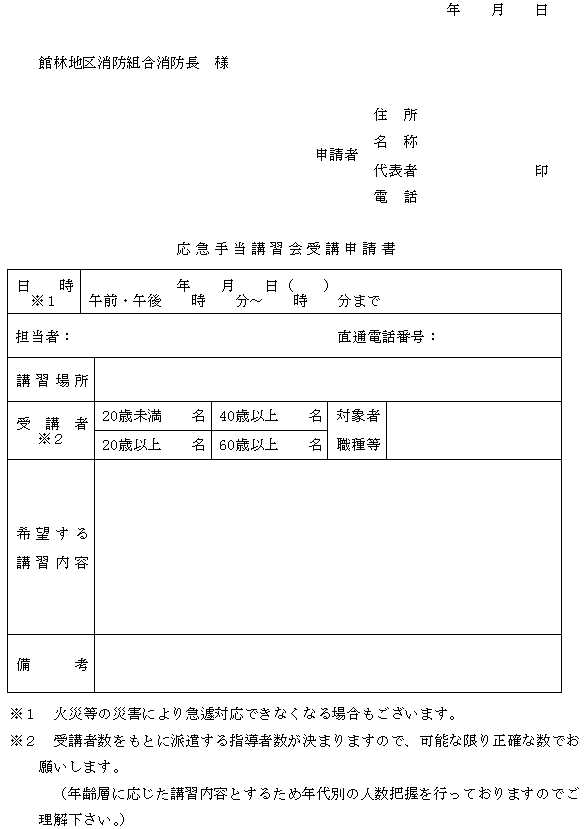 �l����X��
�l����X��
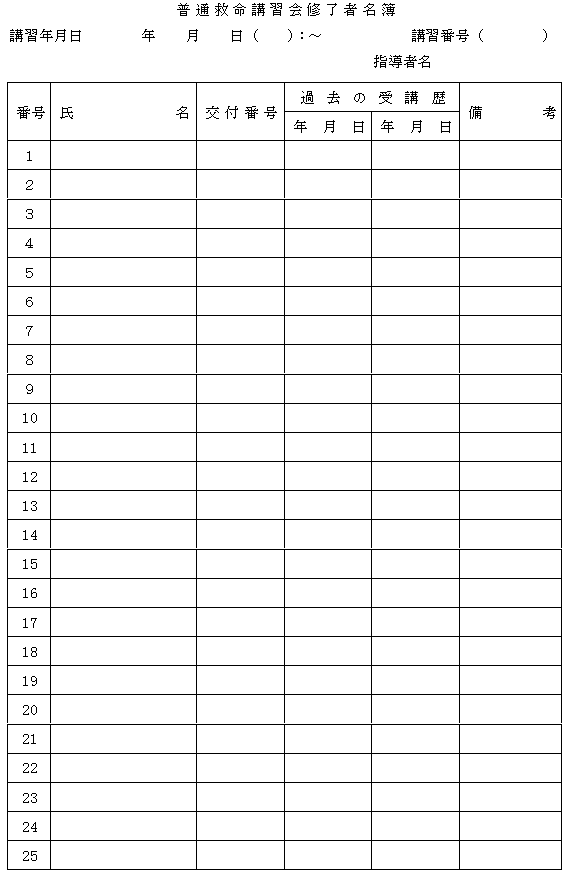 �l����10��
�l����10��
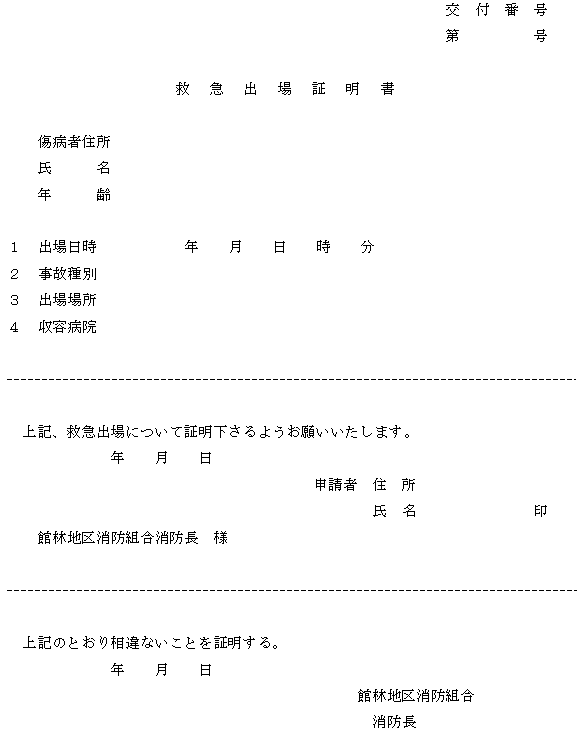
�l����P��
�l����P���i��11���W�j
�l����Q��
�l����R��
�l����S��
�l����T��
�l����U��
�l����V��
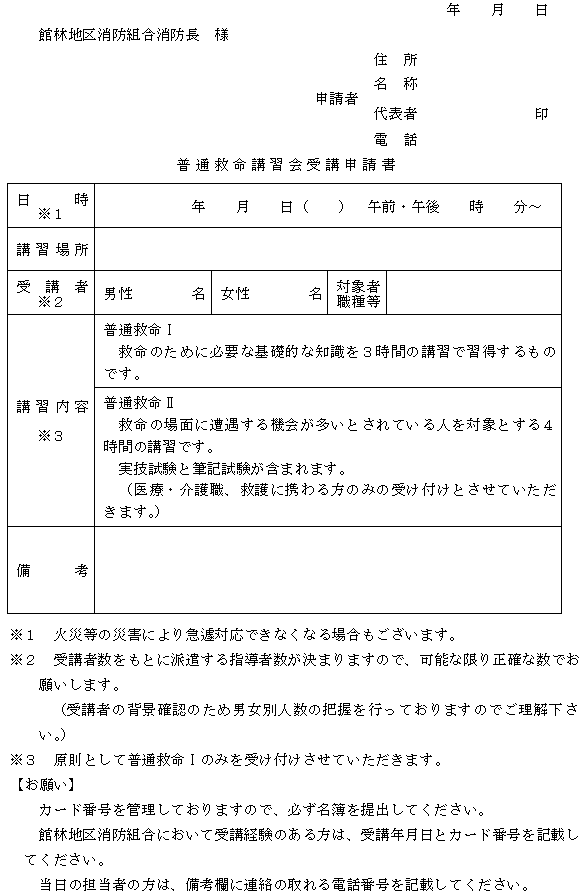
�l����W��
�l����X��
�l����10��