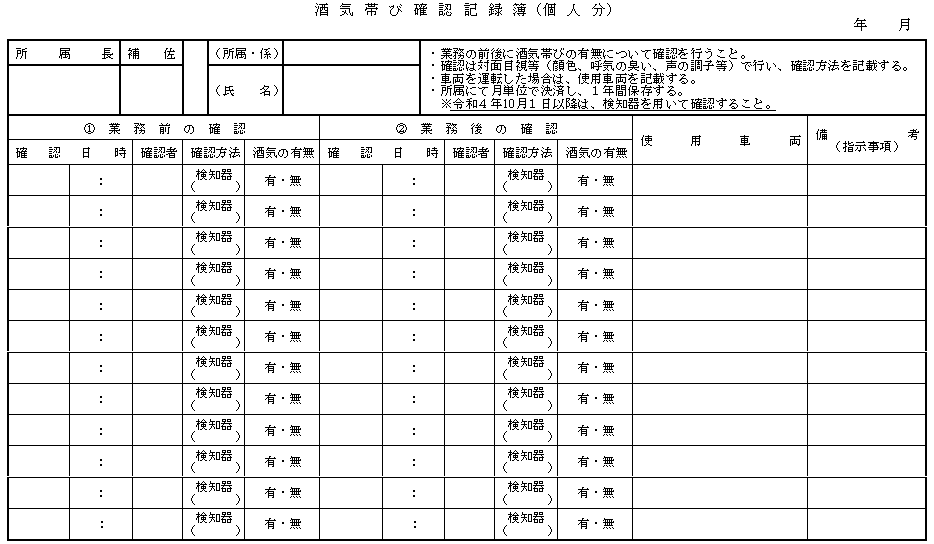館林地区消防組合消防本部機械器具取扱規程
平成29年4月1日
訓令第2号
改正 |
令和2年4月17日訓令第18号 |
令和4年3月31日訓令第10号 |
館林地区消防組合消防署機械器具取扱規程(昭和58年消防長訓令第2号)の全部を次の
ように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防用機械器具(以下「機械器具」という。)の適正な管理及び取
り扱いを図るため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
よる。
(1) 機械器具 消防の用に供する各種自動車、消防舟艇及び消防用機械器具の総称を
いう。
(2) 消防自動車等の車両 火災など災害の状況に応じて適切な消防活動を行うため、
各種の消防用機械器具を装備し、消防のための出動に使用する緊急自動車及びその他
の消防車両の総称をいう。
(3) 所属長 消防本部の課長、消防署長及び分署長をいう。
(4) 機関員認定者 普通自動車については、普通自動車免許を取得後2年が経過し、
当消防組合が定める普通機関員講習を受講した者。大型自動車については、大型自動
車免許を取得し、当消防組合が定める大型機関員講習を受講した者をいう。
(5) 機関員 前号の機関員認定者で勤務日に消防自動車等の車両の運転に従事する者
をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 機械器具の管理については、道路交通法(昭和35年法律第105号)、道路運送車
両法(昭和26年法律第185号)、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)、船
舶法(明治32年法律第46号)その他法令に定めがあるもののほか、この規程の定めると
ころによるものとする。
(機械器具の配置)
第4条 警防課長は、機械器具の機能、消防隊の活動特性等を考慮して、適正に機械器具
を配置しなければならない。
(所属長の責務)
第5条 所属長は、配置されている機械器具の性能の把握に努めるとともに、常に効果的
に利用できるよう、管理の適正化を図らなければならない。
(機械器具取扱者の責務)
第6条 機械器具を取り扱う者は、当該機械器具の適正な管理と取り扱い技術の向上に努
め、その機能を十分に発揮しなければならない。
(消防自動車等の車両の運転資格)
第7条 消防自動車等の車両は、機関員でなければ運転をしてはならない。ただし、業務
執行上、特に必要がある場合で、所属長の承認を得たときは、この限りでない。
(救命索発射銃の所持及び取り扱い)
第8条 警防課長は、救命索発射銃(以下「発射銃」という。)について、銃砲刀剣類所
持等取締法の規定に基づき、適正に維持し、管理しなければならない。
2 発射銃の所持者は、館林消防署長とする。
3 所属長は、特別救助隊員から発射銃を用いて人命救助等に従事する者(以下「発射銃
従事者」という。)を指定するものとする。
4 発射銃は、所持者及び発射銃従事者以外の者が取り扱ってはならない。
(クレーン等の従事)
第9条 次の各号に掲げる運転及び作業は、技能講習修了証等の交付を受けている者以外
の者を、当該作業に従事させてはならない。また、従事する者は、関係法令を遵守する
とともに、安全に配意して、これに従事しなければならない。
(1) クレーン及び玉掛け
(2) 重機
(3) フォークリフト
(4) 長さ3m以上、推進機関の出力1.5kW以上の船舶
(5) 潜水
(6) その他技能講習等が必要な業務
(安全運転管理者等及び整備管理者の選任等)
第10条 安全運転管理者等の選任は道路交通法第74条の3の規定に基づき、整備管理者の
選任は道路運送車両法第50条の規定に基づき、消防長が次のとおり職員を選任するもの
とする。
(1) 安全運転管理者 必要数
(2) 副安全運転管理者 必要数
(3) 整備管理者 必要数
(4) 責任者 必要数
2 安全運転管理者 消防本部警防課長及び各消防署署長補佐若しくは署長補佐の職にあ
るもの。
3 副安全運転管理者 消防本部警防課長補佐の職にあるもの。
4 整備管理者 消防本部警防課長補佐又は係長の職にあるもの。
5 責任者 所属長が指定するもの。
(安全運転管理者等及び整備管理者の選任等の届出)
第11条 消防長は、安全運転管理者等を選任したときは、道路交通法第74条の3第5項の
規定に基づき群馬県公安委員会に届けなければならない。これを解任したときも、同様
とするものとする。
2 消防長は、整備管理者を選任したときは、道路運送車両法第52条の規定に基づき国土
交通省に届けなければならない。これを解任したときも、同様とするものとする。
(安全運転管理者等の処置すべき事項)
第12条 安全運転管理者は、安全な運転を確保するため、道路交通法施行規則(昭和35年
総理府令第60号)第9条の10に定める事項を処理するものとする。
2 副安全運転管理者は、安全運転管理者が処理する事務で、当該安全運転管理者が定め
るものの補助に当たるものとする。
3 安全運転管理者等は、道路交通法施行規則第9条の10第7項に定める事項について、
酒気帯び確認記録簿(様式第5号)に記録し、その記録を1年間保管しなければならな
い。
(整備管理者の任務)
第13条 整備管理者は、消防自動車等の車両の点検及び整備の指導監督等、道路運送車両
法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条に定める任務を行うものとする。
(次長若しくは所属長との調整等)
第14条 安全運転管理者等及び整備管理者は、次長若しくは所属長の指揮監督を受け、安
全運転管理者等及び整備管理者と相互に連携をとり、安全運転確保及び自動車の安全運
行を維持するために必要な点検、整備の内容を把握し、定期点検整備の計画等について
協議するものとする。
2 安全運転管理者等及び整備管理者は、点検及び整備の安全な実施を図るため、車両管
理状況について、毎月1回以上次長若しくは所属長に報告するものとする。
(継続検査等)
第15条 警防課長は、道路運送車両法に定める継続検査及び定期点検(以下「継続検査等」
という。)を適正に実施させなければならない。
2 継続検査等を実施する車両を管理する所属長は、消防自動車等の車両の修理及び継続
申請書(様式第2号)により、警防課長に申請を行う等の必要な処置を講じ、当該継続
検査等を適正に実施しなければならない。
3 所属長は、継続検査等の整備が完了したときは、これを確認し、車両等修理及び継続
結果報告書(様式第4号)により、当該継続検査等の結果を警防課長に報告しなければ
ならない。
(点検)
第16条 機械器具の点検は、次の各号に掲げる区分に応じ、機械器具を取り扱う職員が行
うものとする。
(1) 始業点検 毎日、勤務交代に引き続き、機械器具全般について行う。
(2) 運行前点検 消防自動車等の車両は、始業点検時に機関員が運行前点検表(様式
第1号)に基づき行う。
(3) 使用後点検 機械器具の使用後に、始業点検及び運行前点検に準じて行う。
(4) 月例点検 毎月1回以上、所属で管理する機械器具全般について、次に掲げる項
目により行う。
イ 数量及び保管状況の点検
ロ 消防用自動車等のかじ取り装置、制動装置、走行装置、緩衝装置、動力伝達装置、
電気装置、原動機、ポンプ、はしご装置その他の装置の機能点検及び注油
ハ 携帯無線機、空気呼吸器その他の車両積載品、ホース及びボンベの機能点検
ニ 機械器具全般の機能点検及び注油
(5) 特別点検 所属長が必要と認めた場合に管理する機械器具全般について行う。
2 前項各号に定める点検を実施する者は、点検の結果を速やかに所属長に報告しなけれ
ばならない。
(整備)
第17条 機械器具の整備は、次の各号に掲げる区分に応じ、機械器具を取り扱う職員が行
うものとする。
(1) 日常整備 毎日必要に応じ補給、調整及び清掃その他必要な整備を行う。
(2) 使用後整備 機械器具の使用後に補給、調整及び清掃その他必要な整備を行う。
(3) 月例整備 毎月1回以上、所属で管理する機械器具全般について行う。
(4) 特別整備 所属長が必要と認めた場合に管理する機械器具全般について行う。
2 前項各号に定める整備を実施する者は、整備の結果を速やかに所属長に報告しなけれ
ばならない。
(取り扱いの原則)
第18条 職員は、機械器具を愛護し、その機能に精通し、操作を熟達し、適正な運用に努
めなければならない。
(取り扱いの注意)
第19条 機械器具に共通する取り扱い上の注意事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 機械器具は、機能が正常なものでなければ使用してはならない。ただし、整備終
了までの期間において、主要な機能が安全かつ確実に使用できる場合は、この限りで
ない。
(2) 機械器具は、定められた手順により取り扱うこと。
(3) 機械器具を使用するときは、常に計器等に注意し、異常が認められたときは直ち
に必要な措置を講ずるとともに上司に報告すること。
(4) 機械器具は、その性能及び機能の範囲で使用し粗暴な取り扱いをしないこと。
(5) 機械器具は、汚損及び腐食防止に努め使用後は十分に手入れを行うこと。
(6) 機械器具の燃料は、原則として常時タンク容量の2分の1以上を保持すること。
(7) 機械器具の始動直後は、急激な高速回転を避けること。
(8) 燃料タンク、燃料携行缶及び燃料混合容器に燃料を補給するときは、引火事故に
注意すること。
(修理の申請)
第20条 機械器具の使用者は、機械器具に故障、損傷又は異常を認めたときは、直ちに所
属長に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告を受けた所属長は、その状況を調査し、修理を要すると認める
ときは、次のとおり、警防課長に修理の申請を行う等の必要な処置を講じ、その状況を
明らかにしておかなければならない。
(1) 消防自動車等の車両 消防自動車等の車両の修理及び継続申請書(様式第2号)
(2) その他の機械器具 備品・物品の購入及び修理申請書(様式第3号)
3 前項の申請を受けた警防課長は、その内容を審査し、適当と認めたときは、館林地区
消防組合財務規則(昭和47年規則第1号)の規定に基づき、必要な手続きを行い、修理
等必要な処置を執るものとする。
4 所属長は、修理が完了したときは、これを確認し、車両等修理及び継続結果報告書(
様式第4号)により、修理の結果を警防課長に報告しなければならない。
(部品等の交付)
第21条 所属長は、配置されている機械器具の部品又は消耗品等の供給を受けようとする
ときは、備品・物品の購入及び修理申請書(様式第3号)により、警防課長に、申請し
なければならない。
2 所属長は、配置されている機械器具の部品又は消耗品等について、その状況を明らか
にするとともに、物品の受け払いについて、適正に処理しなければならない。
3 警防課長は、機械器具の部品又は消耗品等の供給の申請に対し、速やかに対応するよ
う努めるものとする。
(燃料等の補給及び交換)
第22条 所属長は、配置されている機械器具の燃料及び潤滑油等の残有量を常に把握し、
機器機能に支障を与えないようこれらを補給しておかなければならない。
2 機械器具の機関装置や変速装置の潤滑油類の交換は、継続検査、定期点検及び指定さ
れた時期に応じて行い、適正に管理するものとする。
(所属及び番号の表示)
第23条 消防用ホース、空気呼吸器用ボンベその他の機械器具で必要と認められるものに
は、所属及び番号の表示を行うものとする。
2 消防用ホースは、次の各号のとおり色分けするものとする。
(1) 65㎜ホース 白色又は黄色
(2) 50㎜ホース 館林消防署(西、北分署) 橙色
板倉消防署 赤色
明和消防署 青色
千代田消防署 黄色
邑楽消防署 緑色
(3) 40㎜ホース 白色
(安全管理)
第24条 所属長は、機器の取り扱いに際し、事故防止を図るため、安全管理の徹底を期さ
なければならない。
(事故防止対策)
第25条 所属長は、事故発生の危険が予測されるときは、事故防止のための適切な処置を
執らなければならない。
(安全運転)
第26条 職員は、消防自動車等の車両の性能、道路、交通及び天候の状況に応じ、安全な
速度と方法で運転しなければならない。
2 安全運転管理者は、消防自動車等の車両の事故防止を図るため、職員に対して必要な
指示及び助言をしなければならない。
(機関日誌等)
第27条 消防自動車等の車両を使用した場合は、勤務日誌に使用状況を記載しなければな
らない。
2 機関員は、一日に使用した消防自動車等の車両の使用状況、運行状況及び給油状況を
機関日誌に記録し所属長に報告しなければならない。
(事故発生時の処置)
第28条 交通事故、機器損傷事故又は機器亡失事故が発生したときは、関係職員は、直ち
に関係法令で定める処置を行うとともに、次により処理しなければならない。
(1) 事故の内容及び発生原因の把握
(2) 所属長への報告
(3) その他必要な処置
(事故報告)
第29条 所属長は、前条に規定する事故が発生したときは、当事者並びに直接指揮監督を
行った者及びその他関係職員に、館林地区消防組合職員交通事故審査会要綱(昭和48年
消防長訓令第1号)の規定に基づき、必要な事項を記載させた報告書を作成させ、総務
課長及び警防課長を経由して、消防長に速やかに報告しなければならない。
2 所属長は、前条に規定する事故のうち、交通事故及び機器の取り扱いに伴って発生し
た人身事故については、前項の規定による報告に先立って、事故の概況を警防課長及び
総務課長を経由して、消防長に報告し、その指示に従うものとする。
(事故調査)
第30条 消防長は、事故の内容、発生原因等について必要があると認めるときは、調査を
行うものとする。
(環境保護)
第31条 職員は、機械器具の効率的な運用に努め、環境汚染の防止及び燃料の合理的な消
費に留意しなければならない。
(非常用燃料の確保)
第32条 所属長は、非常用として常時適量の燃料を確保するように努め、取り扱い及び保
管について、適正を期さなければならない。
(消防機械器具台帳の記録保存)
第33条 所属長は、常に機械器具台帳を整理し、機器管理、点検結果その他の状況等の必
要事項を記録し、保存しておかなければならない。
(その他)
第34条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月17日訓令第18号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日訓令第10号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号
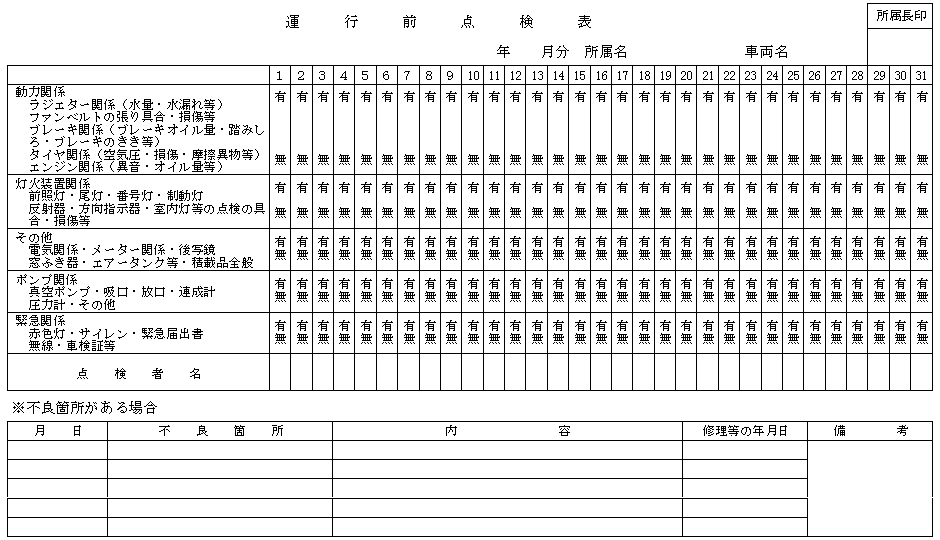 様式第2号
様式第2号
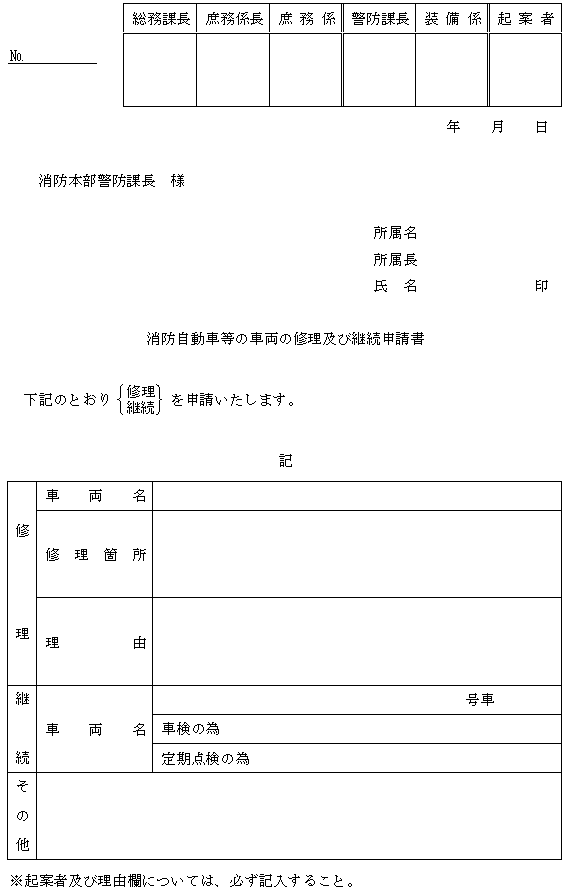 様式第3号
様式第3号
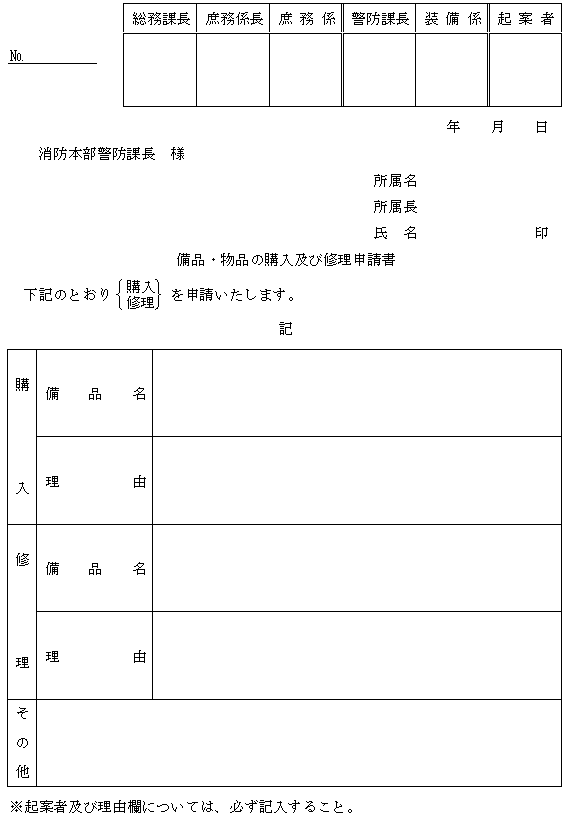 様式第4号
様式第4号
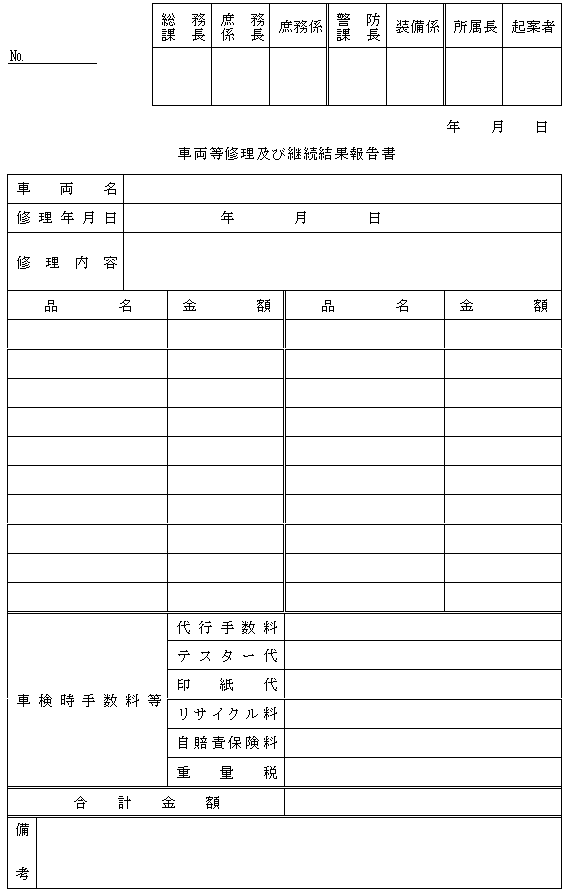 様式第5号
様式第5号
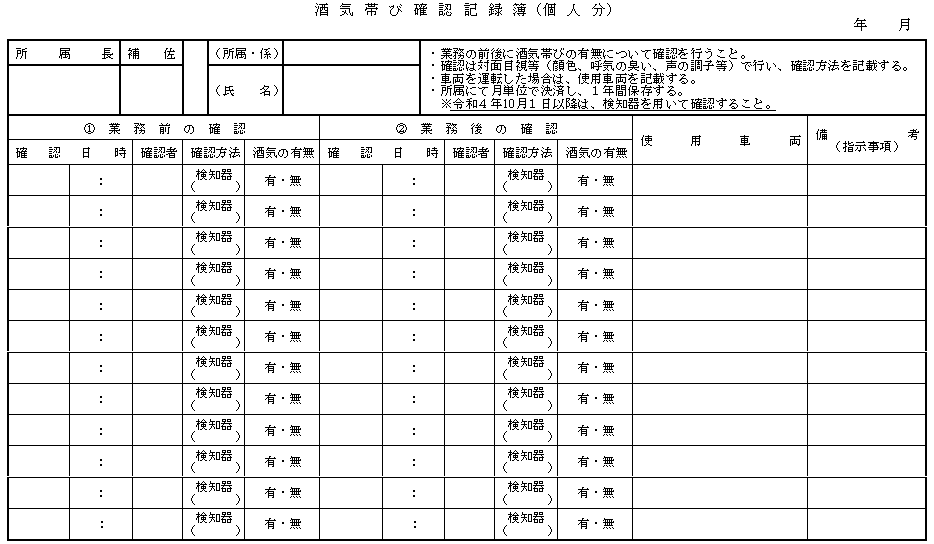
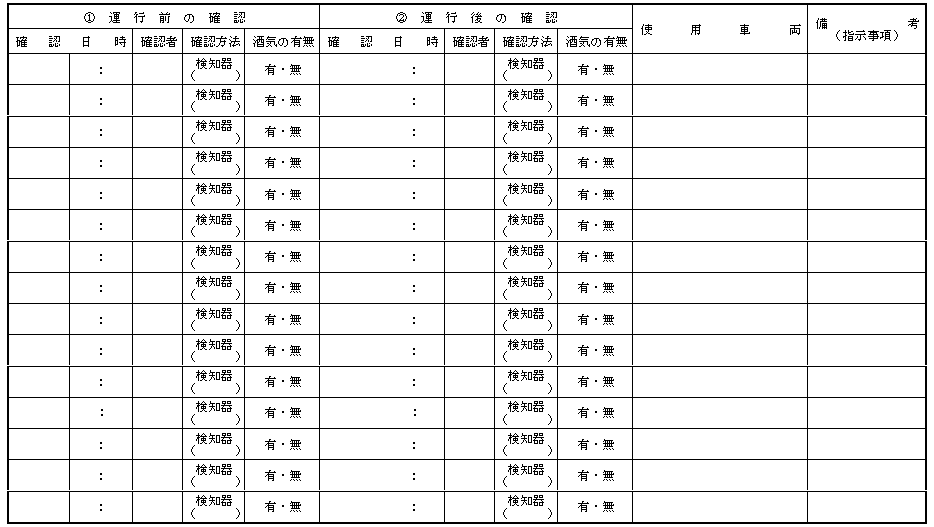
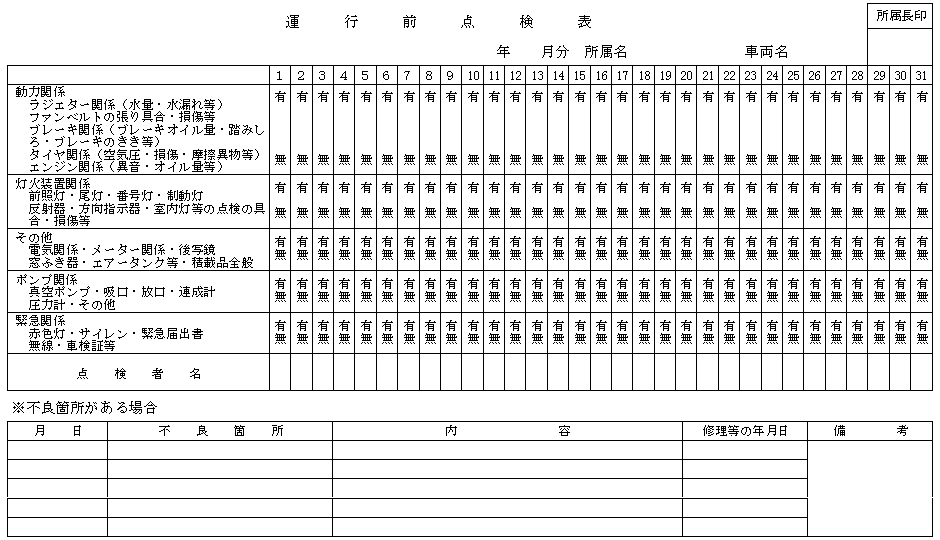 様式第2号
様式第2号
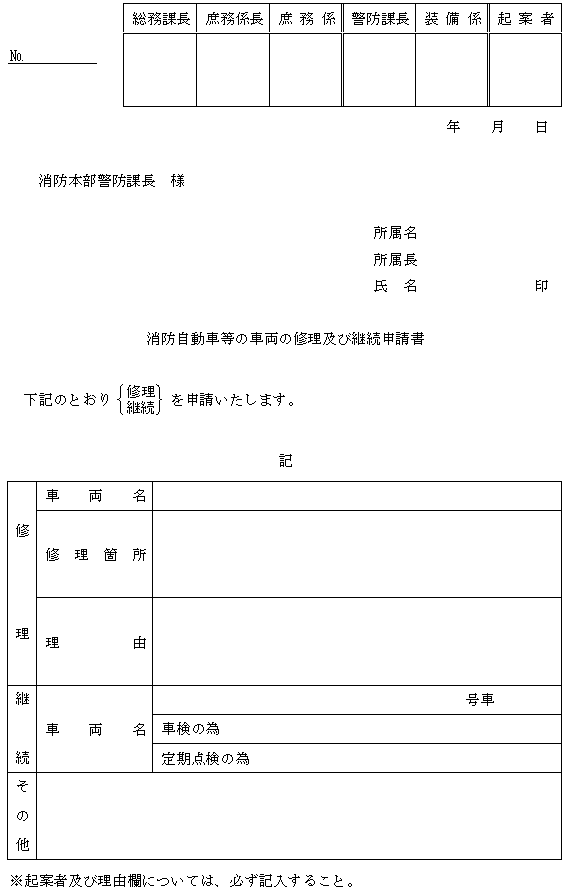 様式第3号
様式第3号
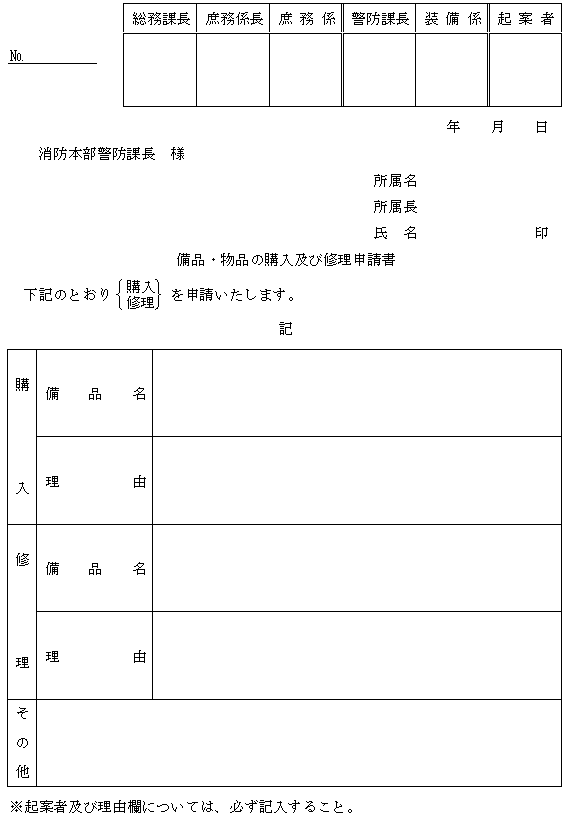 様式第4号
様式第4号
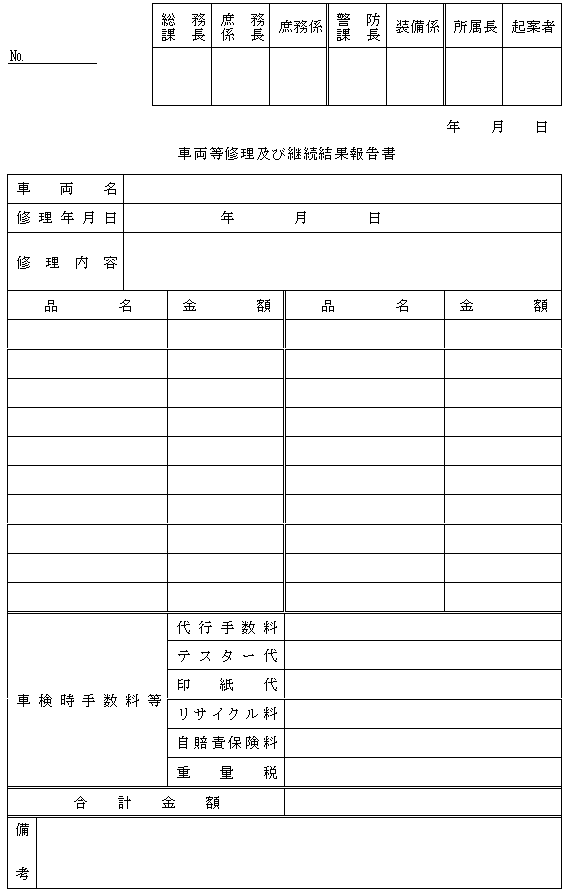 様式第5号
様式第5号
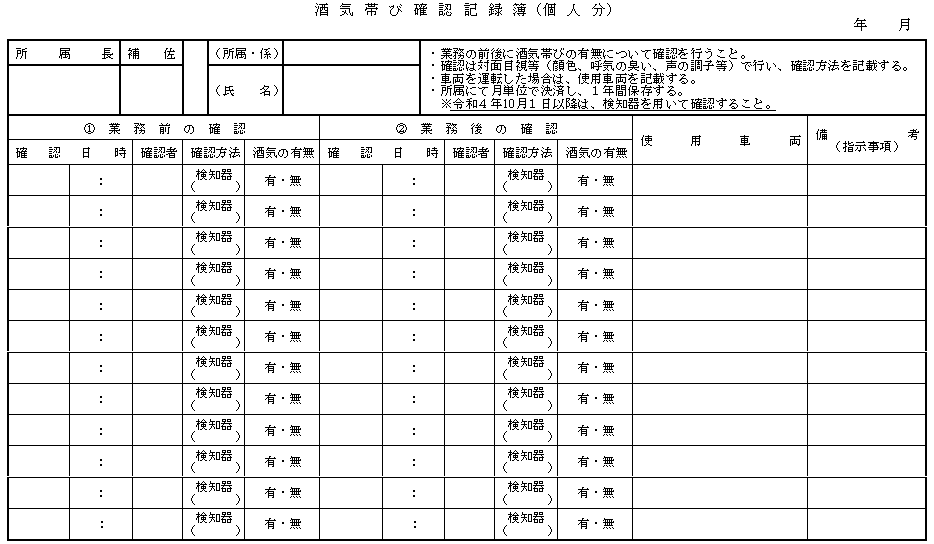
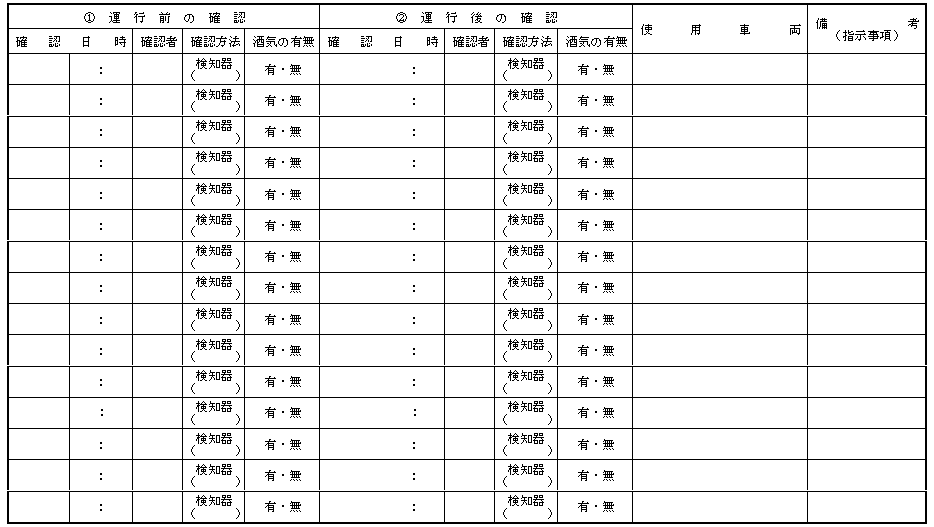
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号