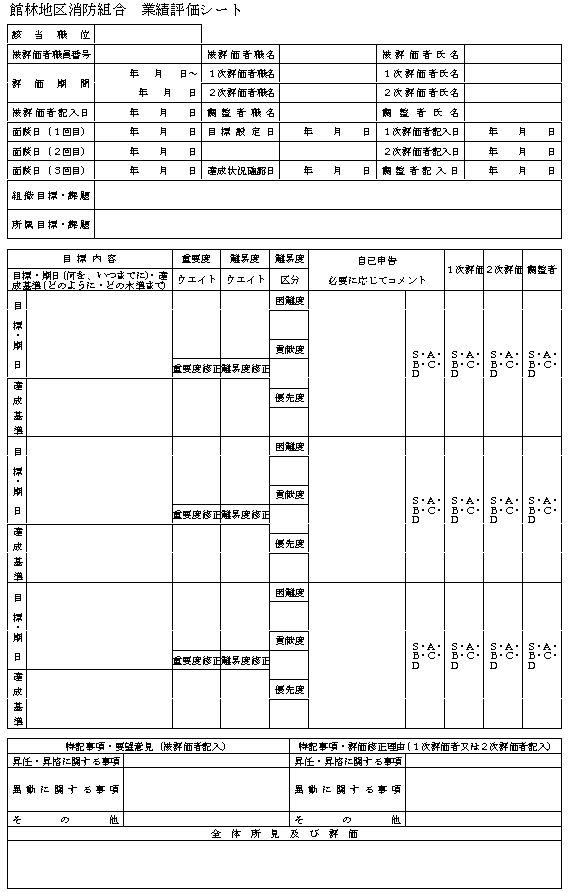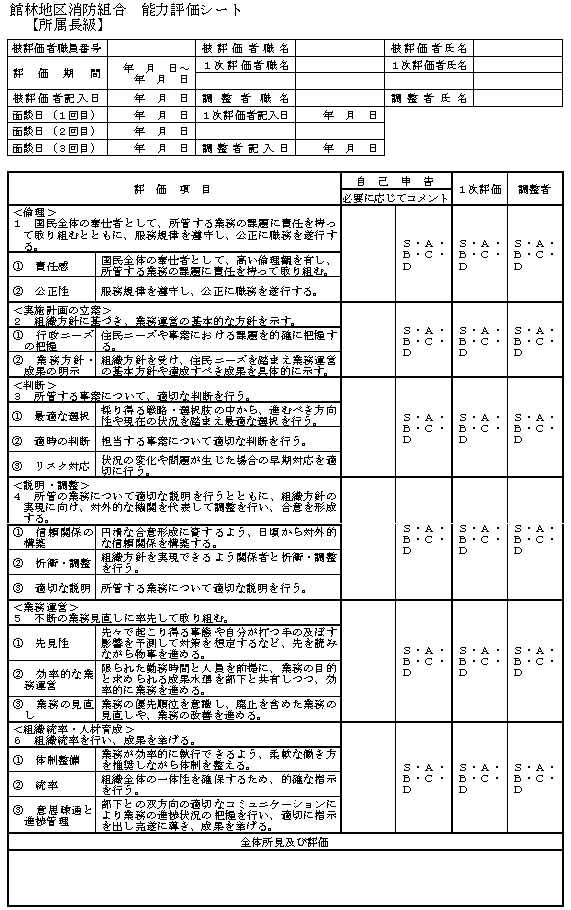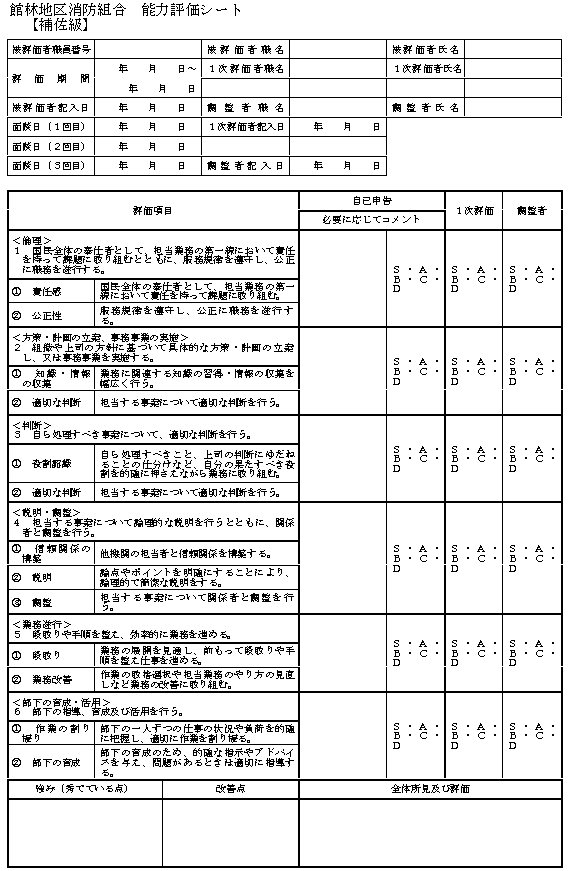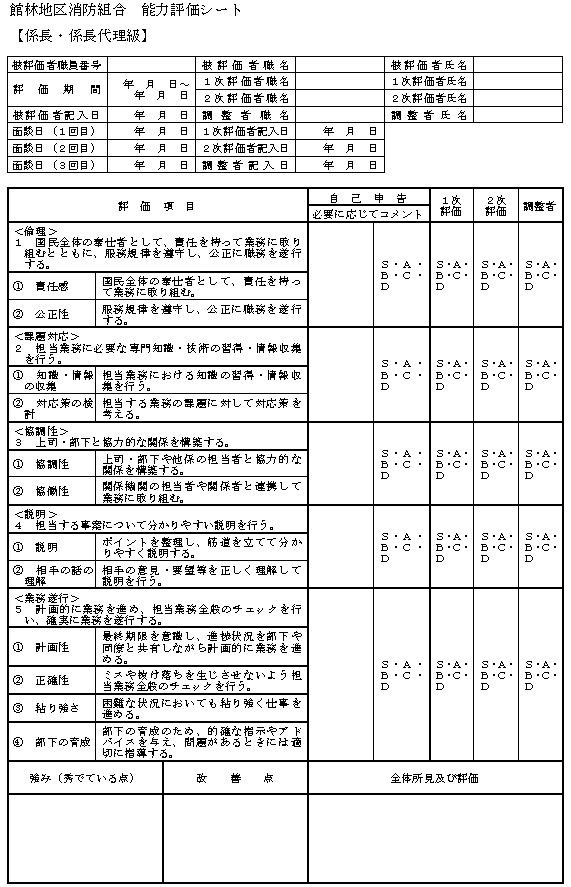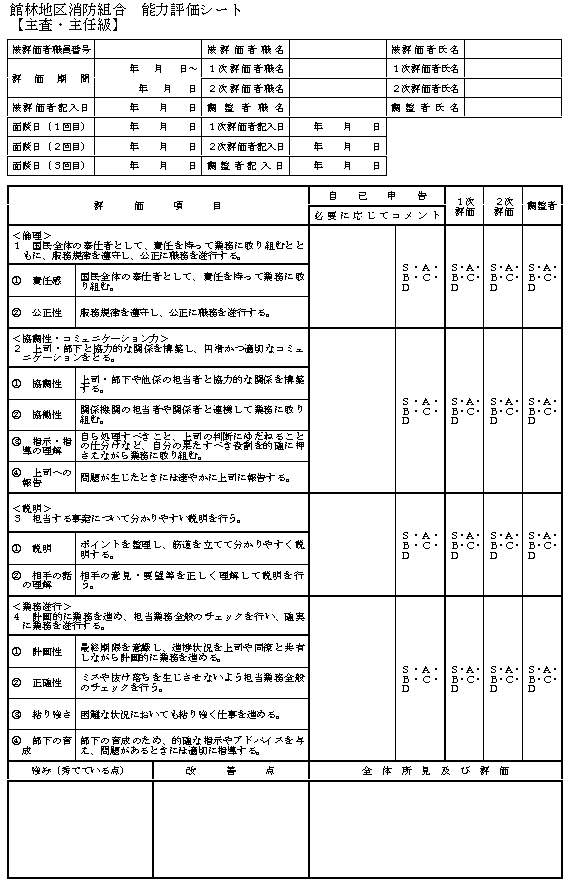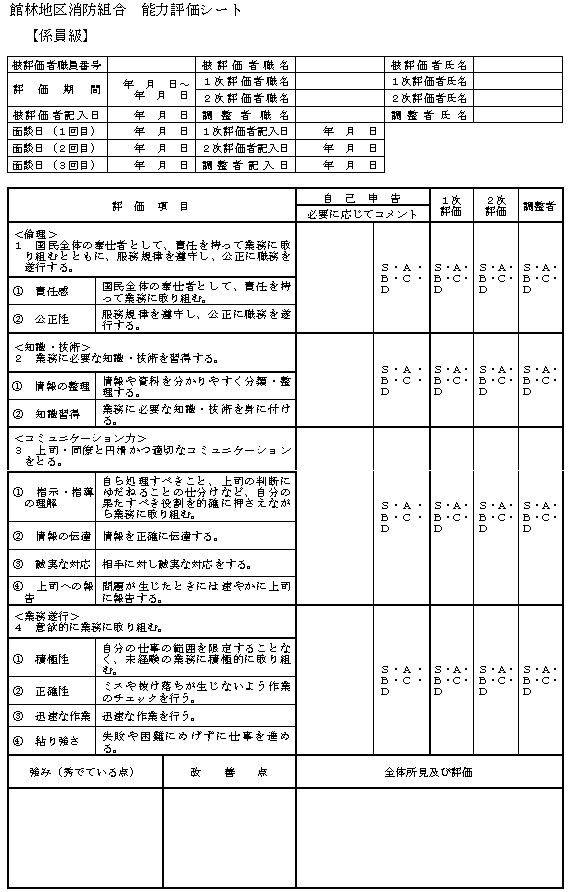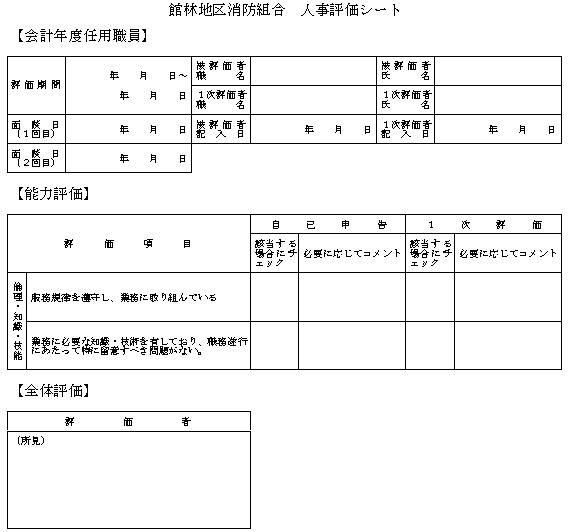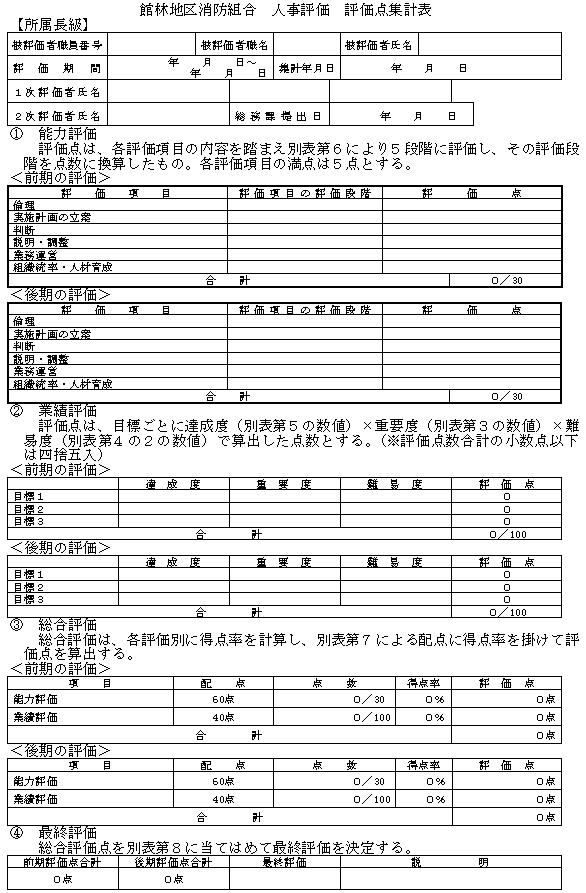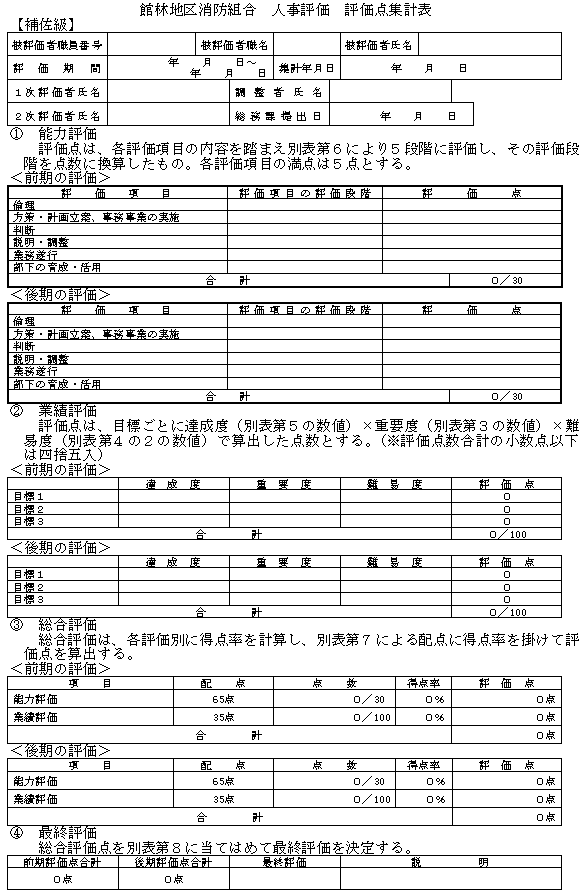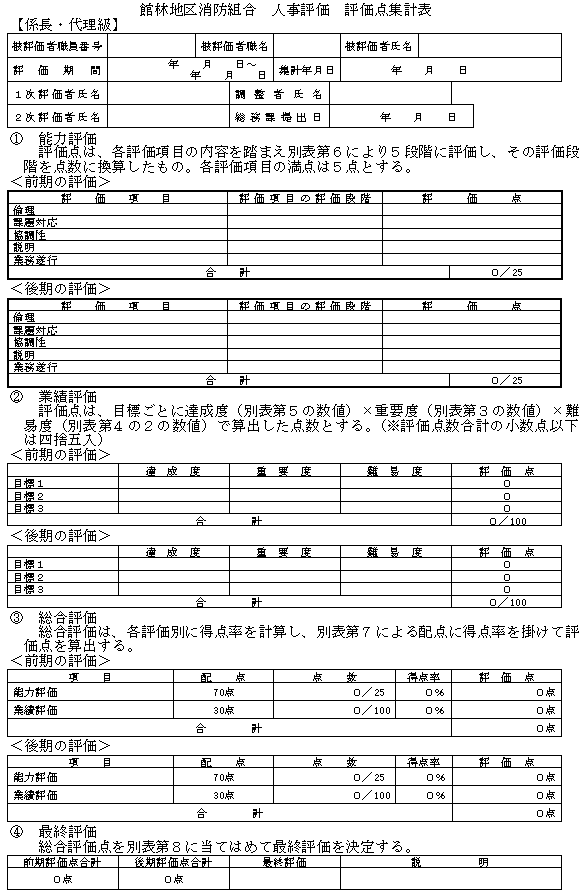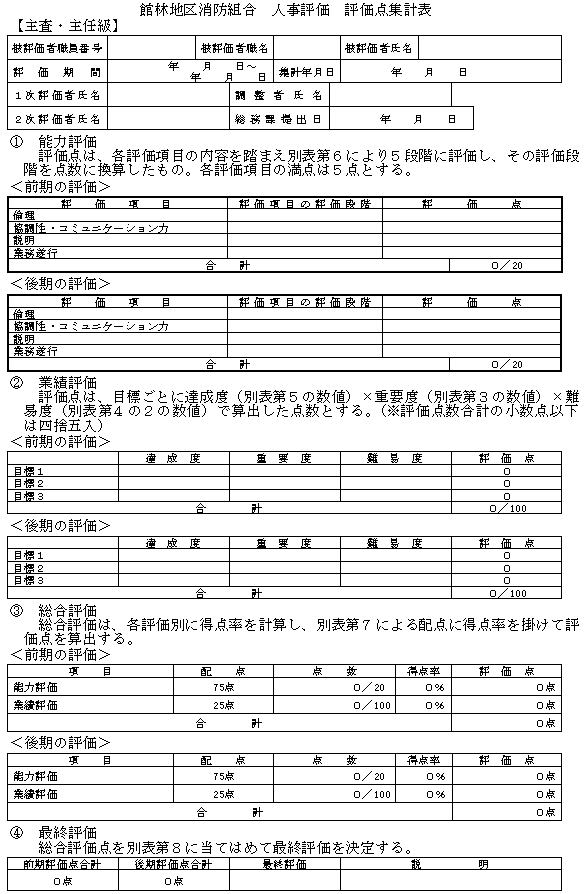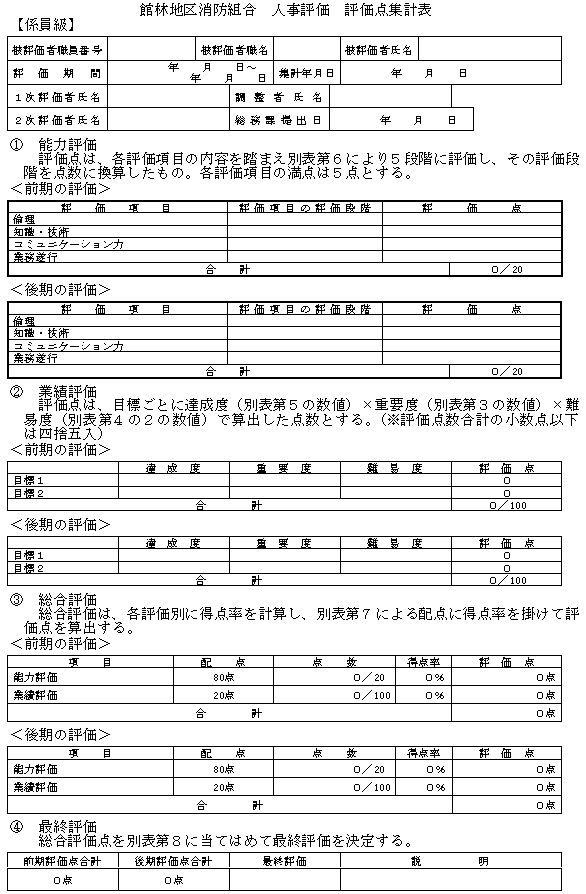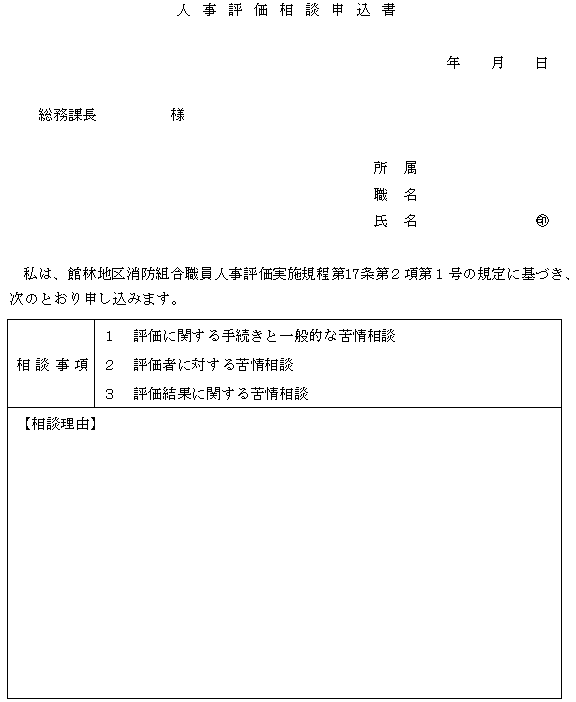�ٗђn����h�g���E���l���]�����{�K��
|
|
|
| ���� | ����31�N�R��14���P�ߑ�S�� | �ߘa�Q�N�P��17���P�ߑ�R�� |
| �ߘa�Q�N�T���V���P�ߑ�16�� | �ߘa�R�N�T��25���P�ߑ�15�� |
| �ߘa�S�N�P���V���P�ߑ�P�� | �ߘa�S�N11��10���P�ߑ�17�� |
| �ߘa�U�N�R��11���P�ߑ�R�� | |
��Q���@���̋K���ɂ����āA�l���]���Ƃ́A���炩���ߐݒ肵���E���ڕW�̒B���x����]������Ɛѕ]�����тɕ]�����ڂ��Ƃɒ�߂�W���E�����s�\�͋y�ђ���_�Ɋ�Â��A�E�����s�̉ߒ��ɂ����Ĕ������ꂽ�E���̔\�͂��q�ϓI�ɕ]������\�͕]������\������A�l���]���̑ΏۂƂȂ���ԁi�ȉ��u�]�����ԁv�Ƃ����B�j�ɂ�����E�����Ƃ̋Ζ����тɂ��Č������K���ɕ]�����邱�Ƃ������B
��R���@�l���]���̎�ނ́A����]���A���ʕ]���y�ђ��ԕ]���Ƃ���B
(�P)�@����]���Ƃ́A���N�Q�����I�Ɏ��{����]���������B
(�Q)�@���ʕ]���Ƃ́A���h�����K�v�ƔF�߂��ꍇ�Ɏ��{����]���������B�Ȃ��A���ԁA������ɂ��Ă͂��̓s�x��߂���̂Ƃ���B
(�R)�@���ԕ]���Ƃ́A�]�����Ԓ��ɏ��C���͈ٓ������E���ɂ��āA���C���͈ٓ��������̑O��������Ƃ����{����]���������B
��S���@�]�����Ԃ͎��̊e���Ɍf����]���̋敪�ɉ����āA���Y�e���ɒ�߂���Ԃɂ����̂Ƃ���B�������A���Y���Ԓ��ɏ��C���͈ٓ������E���ɂ��ẮA���C���͈ٓ��̓����瓖�Y�]�����Ԃ̖����܂łƂ���B
(�P)�@�Ɛѕ]���ɂ����ẮA���N10���P�����痂�N�R��31���܂ŋy�тS���P������X��30���܂łƂ��A���Ԃ̖�����]���̊���Ƃ���B
(�Q)�@�\�͕]���ɂ����ẮA���N10���P�����痂�N�R��31���܂ŋy�тS���P������X��30���܂łƂ��A���Ԃ̖�����]���̊���Ƃ���B
��T���@�l���]���̑Ώێҁi�ȉ��u��]���ҁv�Ƃ����B�j�́A���Ɍf����҂��������ׂĂ̐E���Ƃ���B
(�P)�@�x�E�A�h���A�����̏o�����͌��C���̑��̗��R�ɂ��A�]�����ԓ��ɂ�����Ζ����т��Q���������̎�
(�Q)�@���̑��Ǘ��Җ��͏��h������߂�E��
��U���@�l���]���́A�����ے����������A
�ʕ\��P�̋敪�ɂ�����ɂ������]���҂̏�i�ł���E���i�ȉ��u�]���ҁv�Ƃ����B�j���P���]���ҁA�Q���]���ҋy�ђ����҂Ƃ��ĕ]�����邱�Ƃ������Ƃ���B
�Q�@�]���҂Ƃ��ď�i�̊��Ԃ��R���������̏ꍇ�́A�O�C�҂̈ӌ���������čs�����̂Ƃ���B
�R�@�����ȕ]�����ʂ̊m�ۂƁA�E���l�̑g�D���O�ւ̖����y�ѐӔC�F���̂��߁A��]���Ҏ��g������Ɛѕ]���y�є\�͕]�����s���i�ȉ��u���ȕ]���v�Ƃ����B�j���̂Ƃ���B
�S�@�����ے��́A�K�v�ɉ����ĕ]���҂��w�肷�邱�Ƃ��ł���B
��V���@�l���]�����s���҂͎��̊e���Ɍf���鎖�������炵�A�l���]�����s�����̂Ƃ���B
(�P)�@�]���҂́A�l���]�������Ȃ̏d�v�ȐE�ӂł��邱�Ƃ����o���A�B�R�Ƃ����ԓx�Ɗm�ł���M�O�������ĕ]�����s���A�]����ɂ����Ă͔�]���҂̔\�͂��\���ɔ��������߂�悤�K�ȏ�����w���ɂ��A���S�̑[�u���u���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
(�Q)�@�]���́A��]���҂Ɋւ������̊ώ@���͊m���ȕɂ�蓾�������ɂ��s�����̂ł���A�]�������O�̌��ۂɂ݂̂Ƃ��ꂽ�蕗�]���ɍ��E����Ă͂Ȃ�Ȃ��B
(�R)�@�]���͐E���Ɋւ��Č���ꂽ�E���̎��сA�s���A�ԓx��ΏۂƂ��A�����Ƃ��Č����O�ɂ�����s���A�ԓx�A���͐E���ɒ��ڊW���Ȃ��s�����l���ɓ���Ă͂Ȃ�Ȃ��B
(�S)�@�]���́A��Ί�ɂ����̂Ƃ��A���̐E���Ƃ̑��ݔ�r�ɂ����̂ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�܂��A�]���̔��f�ƂȂ��́A��]���҂̑����鏊���y�ѐE���ӔC���Ƃɒ�߂��Ă���A���̊����ɐ�Ε]�������ŕ]�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
(�T)�@�]���҂́A����̕]���Z�p�̌���ɓw�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂��A�l���]���Ɋւ��m�蓾���閧��R�炵�Ă͂Ȃ�Ȃ��B
��W���@�����ے��́A�]���҂ɑ��āA�]���\�͂̌���̂��߂ɕK�v�Ȍ��C��K�X���{������̂Ƃ���B
��X���@�l���]���́A
�ʕ\��Q�Ɍf����敪�ɉ����A���\�Ɍf����l������p���čs�����̂Ƃ���B
��10���@�Ɛѕ]���́A�Ɛѕ]���V�[�g�i
�l����P���j�ɂ��A���̊e���Ɍf�����菇�ɏ]���čs�����̂Ƃ���B
(�P)�@��]���҂́A�Ɛѕ]���V�[�g�̖ڕW���ڂ��ƂɁA���Y�]�����Ԃ̋Ɩ��Ɋւ���ڕW���L�����A�P���]���҂ɒ�o����B
(�Q)�@�Ɩ����Ɋւ���ڕW�́A�ł�������ʉ��i���l���j��}��A�]�����q�ϓI�ɂł���悤�ɂ��A��ʉ��i���l���j������ȋƖ��ɂ��Ă��A�ł�����肻�̒B�����x������̓I�ɐ�������Ȃǖ��m�ɂ���悤�w�߂邱�ƁB�܂��A�B��������ݒ�ł���Ɩ��ɂ��ẮA�����Ă��̎������L�����邱�ƁB
(�R)�@�P���]���҂́A��]���҂��ݒ肵���e�ڕW�ɂ��āA�ʐڂ�ʂ��đg�D�̋��߂���e�A���x���Ƃ̍��v�A�{�l�̔\�͌���A�J���̎��_����Ó����ɂ��āA��]���Җ{�l�Ƃ̏\���Șb�������̏�A�ڕW�̓��e�ƒB��������肵�A�����āA
�ʕ\��R�ɂ��Ɛѕ]���̏d�v�x�̊���A
�ʕ\��S�̂P�ɂ�莋�_���Ƃ̋敪��ݒ肵�A
�ʕ\��S�̂Q�ɂ��̓�Փx��ݒ肷����̂Ƃ���B
(�S)�@�Ɛѕ]���V�[�g�́A���ׂĂ̋Ɛѕ]�����ڂ̋L���A�����A���ӂ��I��������]������܂ł́A��]���҂̏��������ۊǂ���B�Ȃ��A�]�����ԓ��Ɉٓ����������ꍇ�ɂ́A�Ɛѕ]���V�[�g�͐V���ɍ쐬������̂Ƃ���B
(�T)�@��]���҂́A�]���������P�T�Ԉȓ��ɏ��������Ɛѕ]���V�[�g����̂��A���Y�]�����Ԓ��̊e�ڕW�B���x�����画�f���A
�ʕ\��T�ɒ�߂�Ɛѕ]����̒B���x��ɏ]���āA���ׂĂ̖ڕW�̂T�i�K�]�����s���A���Ȑ\�����ɋL������B�܂��A���Ȑ\�����ɕK�v�ɉ����ăR�����g���L�����A���₩�ɋƐѕ]���V�[�g���P���]���҂ɒ�o����B
(�U)�@�P���]���҂́A��]���Җ{�l�����o�����Ɛѕ]���V�[�g�ɋL�ڂ���Ă��鎩�ȕ]�����ʂ��Q�l�ɂ��A�ʐڂ�ʂ��Ĕ�]���Җ{�l�Ə\���Ɋm�F���A
�ʕ\��T�ɒ�߂�B���x��ɏ]���Ă��ׂĂ̖ڕW�̂S�i�K�]�����s���A�S�̏����y�ѕ]�����L����Q���]���҂ɒ�o����B
(�V)�@�Q���]���҂́A�P���]���҂ɂ��]���ɂ��āA�s�ύt�����邩�ǂ����Ƃ����ϓ_����]�����s���A�K�v�ȏꍇ�͔�]���҂Ɩʐڂ����{���A�܂��A�ꍇ�ɂ���Ă͂P���]���҂ɍĕ]�����s�킹�邱�Ƃ��ł�����̂Ƃ���B�Q���]���҂́A
�ʕ\��T�ɒ�߂�B���x��ɏ]���ĂS�i�K�]���ɂ�蒲�����s������A�K�v�ɉ����đS�̏����y�ѕ]�����L����A�����҂ɕ]�����ʂ��������o������̂Ƃ���B
(�W)�@�����҂́A�Q���]���҂ɂ�钲���ɂ��ĐR�����s���A�K���łȂ��ƔF�߂��ꍇ�ɂ͂Q���]���҂ɍĒ������s�킹�������ŁA�Ɛѕ]�����K���ł���|�̊m�F���s���B�܂��A�Ɛѕ]���̏d�v�x�y�ѓ�Փx�ɂ��ĐR�����s���A�K���łȂ��ƔF�߂��ꍇ�ɂ́A�d�v�x�y�ѓ�Փx�̏C����������̂Ƃ���B
��11���@�\�͕]���́A�\�͕]���V�[�g�i
�l����Q���̂P�`��Q���̂T�j�ɂ��A�]�����ڂ��Ƃ̓��e�Ɋ�Â��āA���̊e���Ɍf����菇�ɏ]���čs�����̂Ƃ���B
(�P)�@��]���҂́A�]������ɂ����āA�e�]�����ڂ̓��e�A�ԓx�A�s����������̐E�����s�̒��Ŏ�����Ă������ۂ��肵�A
�ʕ\��V�ɒ�߂�]�������ɂT�i�K�Ŏ��ȕ]�����s���ƂƂ��ɁA���Ȑ\�����ɕK�v�ɉ����ăR�����g�����A���₩�ɂP���]���҂ɒ�o����B
(�Q)�@�P���]���҂́A��]���Җ{�l�����o�����\�͕]���V�[�g�ɋL�ڂ���Ă��鎩�ȕ]�����ʂ��Q�l�ɂ��A�ʐڂ�ʂ��Ĕ�]���Җ{�l�Ə\���Ɋm�F���A
�ʕ\��U�ɒ�߂�]�������ɂT�i�K�]�����s���A�]�����R���L����Q���]���҂ɒ�o����B
(�R)�@�Q���]���҂́A�P���]���҂ɂ��]���ɂ��āA�s�ύt�����邩�ǂ����Ƃ����ϓ_����]�����s���A�K�v�ȏꍇ�͔�]���҂Ɩʐڂ����{���A�܂��A�ꍇ�ɂ���Ă͂P���]���҂ɍĕ]�����s�킹�邱�Ƃ��ł�����̂Ƃ���B�Q���]���҂́A
�ʕ\��U�ɒ�߂�B���x��ɏ]���ĂT�i�K�]���ɂ�蒲�����s������A�K�v�ɉ����ĕ]�����L�����A�����҂ɕ]�����ʂ��������o������̂Ƃ���B
(�S)�@�����҂́A�Q���]���҂ɂ�钲���ɂ��ĐR�����s���A�K���łȂ��ƔF�߂��ꍇ�ɂ͂Q���]���҂ɍĒ������s�킹�������ŁA�\�͕]�����K���ł���|�̊m�F���s���B
��12���@���ׂĂ̕]�����I���������_�ŁA�]���҂�
�ʕ\��Q�Ɍf����敪�ɉ������]���_�W�v�\�i
�l����R���̂P�`��R���̂T�j�ɂ��A
�ʕ\��V�̔z�_�Ɋ�Â������]���̕]���_���v�Z���A
�ʕ\��W�ɒ�߂�S�i�K�]���ɂ��ŏI�]�����s�����̂Ƃ��A�I����ɕ]���_�W�v�\���ے��֒�o����B
�Q�@�����ے��́A��o���ꂽ�]���W�v�\���m�F���A�������Ƃɕs�ύt������ꍇ�́A�������s�����̂Ƃ���B
��13���@�]���҂́A�]���̒������I�������ɁA��]���҂̋Ɛѕ]���y�є\�͕]���̌��ʂ��A��]���Җ{�l�ɂ̂݊J������B
�Q�@�]���҂́A�O���̊J�����s��ꂽ��ɁA��]���҂Ɩʐڂ��s���A�]�����ʋy�т��̍����ƂȂ鎖���Ɋ�Â��A�w���y�я������s���B
��14���@��o�����́A���̂Ƃ���Ƃ���B
(�P)�@���ȕ]���́A�Ɛѕ]���y�є\�͕]���̕]���������Q�T�Ԉȓ��ɍs���A�Ɛѕ]���V�[�g�y�є\�͕]���V�[�g���P���]���҂ɒ�o������̂Ƃ���B
(�Q)�@�P���]���҂́A��]���҂��e�]���V�[�g�̒�o���A�]������̗��������܂łɖʐړ����I�����A�Ɛѕ]���V�[�g�y�є\�͕]���V�[�g���Q���]���҂ɒ�o������̂Ƃ���B
(�R)�@�Q���]���҂́A�P���]���҂��e�]���V�[�g�̒�o����������A�Q�T�Ԉȓ��ɒ������I�����A�Ɛѕ]���V�[�g�y�є\�͕]���V�[�g���҂ɒ�o������̂Ƃ���B
(�S)�@�����҂́A�Q���]���҂��e�]���V�[�g�̒�o����������A�Q�T�Ԉȓ��ɒ������I������B
��15���@�l���]���Ɋւ���]���V�[�g���̋L�^�̕ۊǎ҂͑����ے��Ƃ��A��12���̍ŏI�]�����I���������̗�������N�Z���ĂT�N�Ԃ͔p�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
��16���@�l���]���̌��ʂ́A��]���҂̔C�p�A���^�A�������̑��̐l���Ǘ��̊�b�Ƃ��Ċ��p������̂Ƃ���B
�Q�@�]���҂́A�l���]���̌��ʂ�E���̐l�ވ琬���ɐϋɓI�Ɋ��p����悤�w�߂���̂Ƃ���B
�R�@�����ے��́A��]���҂̐l���]����l�����x�Ɍ��ʓI�ɔ��f����悤�ɓw�߁A�E���S�̂̎m�C�����߂�ƂƂ��ɁA�X�Ȃ�\�͂̊J���𑣂����߁A������̎w���A���C�̎��{�A�z�u�������̑��K���ƔF�߂�[�u���u������̂Ƃ���B
��17���@��13���P���̋K��Ɋ�Â��J�����ꂽ�Ɛѕ]���y�є\�͕]���̌��ʂɊւ���E���̋��֑Ή����邽�߁A���k�y�ы����̎葱����݂�����̂Ƃ���B
�Q�@�l���]���̋��̑��k�́A���̊e���ɂ��t���邱�ƂƂ��A���̎��ɂ���Đ\���o�������҂��A����𗝗R�Ƃ��ĕs���v�Ȏ戵�����邱�Ƃ͂Ȃ��B
(�P)�@��]���҂́A�l���]�����k�\�����i
�l����S���j�ɗ��R��t���āA�Ɛѕ]���y�є\�͕]���̌��ʂ��J�����ꂽ������N�Z���ĂP�T�Ԉȓ��ɁA�����ے��ɒ�o������̂Ƃ���B
(�Q)�@���k�ɂ������́A�]���҂�莖���̏�A�����ے���������s���B
(�R)�@�J�����ꂽ�]�����ʂɊւ�������́A���Y�]���̕]�����Ԃɂ��P��Ɍ����t������̂Ƃ���B
�i��v�N�x�C�p�E���̐l���]���̎菇�j
��18���@��v�N�x�C�p�E���̋Ɛѕ]���y�є\�͕]���́A�l���]���V�[�g�i
�l����Q���̂T�j�ɂ��A���̊e���Ɍf�����菇�ɏ]���čs�����̂Ƃ���B
(�P)�@��]���҂́A���Y�]�����Ԓ��̔\�͕]���̊e���ڂ̓��e�肵�A���ȕ]�����s���A�K�v�ɉ����ăR�����g���L����A���₩�ɂP���]���҂ɒ�o����B
(�Q)�@�P���]���҂͔�]���Җ{�l�����o�����l���]���V�[�g�ɋL����Ă��鎩�ȕ]�����ʂ��Q�l�ɂ��A�ʐڂ�ʂ��Ĕ�]���Җ{�l�Ɗm�F���A�S�̕]�����L���㑍���ے��֒�o����B
��19���@���̋K���ɒ�߂���̂̂ق��A�E���̐l���]���Ɋւ��K�v�Ȏ����y�ѕ]�����ʂ̊��p�Ɋւ��鎖���́A���h�����ʂɒ�߂�B
�P�@���̋K���́A����28�N�S���P������{�s����B
�i�ٗђn����h�g���E���Ζ��]��K���̔p�~�j
�Q�@�ٗђn����h�g���E���Ζ��]��K���i����18�N���h���P�ߑ�R���j�͔p�~����B
���@��
�i����31�N�R��14���P�ߑ�S���j ���̌P�߂́A����31�N�S���P������{�s����B
���@��
�i�ߘa�Q�N�P��17���P�ߑ�R���j ���̋K���́A�ߘa�Q�N�S���P������{�s����B
���@��
�i�ߘa�Q�N�T���V���P�ߑ�16���j ���̌P�߂́A�ߘa�Q�N�U���P������{�s����B
���@��
�i�ߘa�R�N�T��25���P�ߑ�15���j ���̌P�߂́A�ߘa�R�N�U���P������{�s����B
���@��
�i�ߘa�S�N�P���V���P�ߑ�P���j ���̌P�߂́A�ߘa�S�N�S���P������{�s����B
���@��
�i�ߘa�S�N11��10���P�ߑ�17���j ���̌P�߂́A�ߘa�T�N�S���P������{�s����B
���@��
�i�ߘa�U�N�R��11���P�ߑ�R���j ���̌P�߂́A�ߘa�U�N�S���P������{�s����B
|
|
|
|
|
�敪 | ��]���ҁi�E�ʁj | �P���]���� | �Q���]���� | ������ |
���h�{���E���E���h���E�� | ���h�� | �Ǘ��� | | |
���� | ���h�� | | |
�Q���E�����E�ے� | ���� | ���h�� | |
| �⍲�E�劲 | �Q���A�����A�ے����͕����� | ���� | �����ے� |
| �W���E�W���㗝 | �⍲���͎劲 | �������͉ے� | �����ے� |
| �卸�E��C�E�W | �⍲�A�劲���͌W�� | �������͉ے� | �����ے� |
| ��v�N�x�C�p�E�� | �ے� | | |
�ʕ\��Q
�i��X���y�ё�12���W�j
|
|
|
|
�敪 | �Ɛѕ]���V�[�g | �\�͕]���V�[�g | �]���_�W�v�\ |
���h���E���� | �l����P�� | �l����Q���̂P | �l����R���̂P |
�Q���E�����E�ے� | | | |
�⍲�E�劲 | | �l����Q���̂Q | �l����R���̂Q |
�W���E�W���㗝 | | �l����Q���̂R | �l����R���̂R |
�卸�E��C | | �l����Q���̂S | �l����R���̂S |
�W | | �l����Q���̂T | �l����R���̂T |
��v�N�x�C�p�E�� | | �l����Q���̂U | |
|
|
���� | �]��� |
�d�v�x | ���ꂼ��̖ڕW�̏d�v�x�����v����100�i�E�G�C�g�j�ɂȂ�悤�ɐݒ肷��B�P�̖ڕW�ɂ��Ă̏d�v�x�̍ő��50�i�E�G�C�g�j�Ƃ���B |
�ʕ\��S�̂P
�i��10���R���W�j
|
|
|
|
|
|
|
�敪 | ���� | �r | �` | �a | �b | �c |
���_ |
����x | �ۑ� | �E����ȉۑ��啝�Ȑ��x�̌������Ɋւ���ڕW �E���N�̌��Ď�������������ڕW | �E���x�̌������Ɋւ���ڕW �E���Ď�������������ڕW | | | |
| ���� | �E�������K�v�Ȓ��O�̊W�@�ցE�����������A�����ɑ����̎��Ԃ�m���J�͂��K�v�ȖڕW | �E�������K�v�Ȓ����O�̊W�@�ցE����������A�����Ɏ��Ԃ�m���J�͂��K�v�ȖڕW | �E�������K�v�Ȓ����O�̊W�@�ւ�����A�����̎��Ԃ�J�͂�������x�K�v�ȖڕW | �E�������ł̒������K�v�ȖڕW | �E�����̕K�v�̂Ȃ��l���x���̖ڕW |
| �n�ӍH�v | �E�ڕW�B���Ɍ����č��x�̑n�ӍH�v��ɂ߂đ����̓w�͂��K�v�Ƃ����ڕW | �E�ڕW�B���Ɍ����ĐV���ȑn�ӍH�v�⑽���̓w�͂��K�v�Ƃ����ڕW | �E�ڕW�B���Ɍ����đn�ӍH�v��w�͂�������x�K�v�Ƃ����ڕW | �E�ڕW�B���Ɍ����ēw�͂�������x�K�v�Ƃ����ڕW | �E���L�ɊY�����Ȃ��ʏ�Ɩ��͈̖̔͂ڕW |
�v���x | �s���ۑ� | �E�s���ۑ�Ƃ��ďd�v�x���ɂ߂č����ڕW | �E�s���ۑ�Ƃ��ďd�v�x�������ڕW | �E�g�D�ڕW�ɍv������ڕW | �E�����ڕW�ɍv������ڕW | �E���L�ɊY�����Ȃ��l���x���̖ڕW |
| �������� | �E�ɂ߂đ傫�Ȍo��ߌ��E�������P�������܂��ڕW �E�����m�ۂɑ傫���v�����邱�Ƃ������܂��ڕW | �E�傫�Ȍo��ߌ��E�������P�������܂��ڕW �E�����m�ۂɍv�����邱�Ƃ������܂��ڕW | �E������x�̌o��ߌ��E�������P�������܂��ڕW | �E�������P�E�Ɩ������̉��P�������܂��ڕW | �E���L�ɊY�����Ȃ��ڕW |
| �Ɩ��� | �E�ɂ߂đ���ȋƖ��ʂ������܂��ڕW | �E����ȋƖ��ʂ������܂��ڕW | �E�ʏ�͈̔͂̋Ɩ��ʂ������܂��ڕW | �E�ʏ�͈̔͂������Ɩ��ʂ������܂��ڕW | �E�ʏ�͈̔͂�傫�������Ɩ��ʂ������܂��ڕW |
�D��x | ���ԓI���� | �E�g�D�ڕW�̒B���ɑ��鎞�ԓI���ɂ߂ċ����ً}����v����ڕW | �E�g�D�ڕW�̒B���ɑ��鎞�ԓI�������ڕW | �E�g�D�ڕW�̒B���ɑ��鎞�ԓI������ڕW | �E�g�D�ڕW�̒B���ɑ��鎞�ԓI����͂��邪�D��x�̒Ⴂ�ڕW | �E���ԓI����̂Ȃ��ڕW |
�ʕ\��S�̂Q
�i��10���R���W�j
|
|
|
��Փx | ���Z�_ | ���_�ʖڕW���x���敪�\�Ƃ̊W |
��(�r) | 120�� | �u����x�v���u�r�v�ł���A���u�v���x�v�u�D��x�v����������u�`�v�ȏ�B |
����(�`) | 110�� | �@�@���_�̂����ꂩ�Ɂu�r�v������B |
| | �A�@���_�Ɂu�`�v�ȏオ�Q����B |
����(�a) | 100�� | �@�@���_�̂����ꂩ�Ɂu�`�v������B |
| | �P���_�Ɂu�a�v�ȏオ�Q����B |
����(�b) | 85�� | �@�@���_�̂����ꂩ�Ɂu�a�v������B |
| | �P���_�Ɂu�b�v�ȏオ�Q����B |
��(�c) | 70�� | ��L�ɊY�����Ȃ��B |
�ʕ\��T
�i��10���T���A��U���A��V���W�j
|
|
|
�]�� | �B���x | ��ʖڕW |
�i���l���ł�����́j |
�r | 100 | �B��������Ȃ����A��������̎^����邭�炢�̌����Ȑ��ʁB |
�` | 85 | �B�����������A���҈ȏ�̐��ʁB |
�a | 75 | �B������N���A�[���A���҂ǂ���̐��ʁB |
�b | 65 | �B�������≺��������A�T�ˊ��҂ǂ���̎��Ȃ̔[���ł��鐬�ʁB |
�c | 50 | �B�������������B |
�]�� | �B���x | �萫�ڕW |
�i���l���ł��Ȃ����́j |
�r | 100 | ���҂�傫�����鎿�̗ǂ����e�A�Ⴕ���͊�����葁���ł���������̎^�ł��錰���Ȑ��ʂ��������B |
�` | 85 | ���҂������鐬�ʂŁA���e�Ɗ������\���葁���ł����B |
�a | 75 | ���҂ǂ���̐��ʂŁA���e�Ɗ������\��ǂ���ł����B |
�b | 65 | �T�ˊ��҂ǂ���̎��ȂŔ[���ł�����x�̐��ʂł������B |
�c | 50 | �w�͂͂��Ă��邪���ʂ��Ȃ��A���͌���ێ��B |
�ʕ\��U
�i��11���P���A��Q���A��R���W�j
|
|
|
�]���i�K�i���v�j | �]���ҕ]�� | �����]�����̊��Z�_�� |
�r | ���߂���s�����m���ɂƂ��Ă���A�t�����l�ށA���̐E���̖͔͂ƂȂ�Ȃǂ̐E�����s�ł���B | �T�_�Ɋ��Z |
�` | ���߂���s�����m���ɂƂ��Ă����B | �S�_�Ɋ��Z |
�a | ���߂���s���������ނ˂Ƃ��Ă����B�i�ʏ�j | �R�_�Ɋ��Z |
�b | ���߂���s�����Œ���͂Ƃ��Ă����B�i�ł����ꍇ�����������A�ł��Ȃ��������Ƃ̕��������ȂǁA�����Ĕ��f����A�Ƃ��Ă����s����������Ȃ������j | �Q�_�Ɋ��Z |
�c | ���߂���s�����S���Ƃ��Ă��Ȃ������B | �P�_�Ɋ��Z |
|
|
|
|
|
|
���� | �z�_ |
�������� | �⍲�� | �W���E�W���㗝�� | �卸�E��C�� | �W���� |
�\�͕]�� | 60�_ | 65�_ | 70�_ | 75�_ | 80�_ |
�Ɛѕ]�� | 40�_ | 35�_ | 30�_ | 25�_ | 20�_ |
���v | 100�_ | 100�_ | 100�_ | 100�_ | 100�_ |
|
|
|
�]�� | ���_���v | ���� |
�` | 75�_�ȏ� | ���ɗD�G�ł��� |
�a | 60�_�ȏ�74�_�ȉ� | �D�G�ł��� |
�b | 45�_�ȏ�59�_�ȉ� | �ǍD�ł��� |
�c | 44�_�ȉ� | �ǍD�ł͂Ȃ� |

�l����P��
�i��10���W�j 
�l����Q���̂P
�i��11���W�j 
�l����Q���̂Q
�i��11���W�j 
�l����Q���̂R
�i��11���W�j 
�l����Q���̂S
�i��11���W�j 
�l����Q���̂T
�i��11���W�j 
�l����Q���̂U
�i��18���W�j 
�l����R���̂P
�i��12���W�j 
�l����R���̂Q
�i��12���W�j 
�l����R���̂R
�i��12���W�j 
�l����R���̂S
�i��12���W�j 
�l����R���̂T
�i��12���W�j 
�l����S��
�i��17���Q����P���W�j